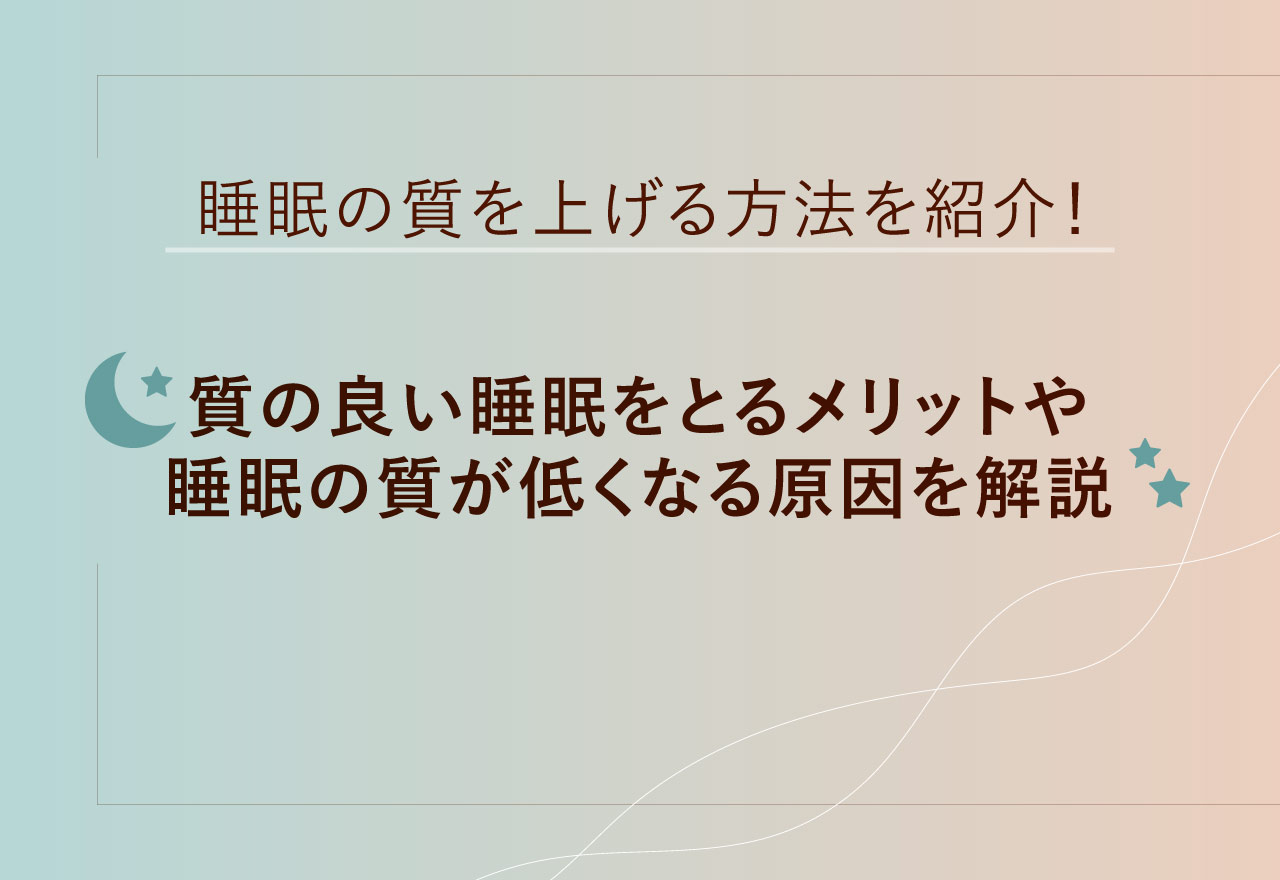目次
睡眠の質が良い状態とは
睡眠の質が良い状態とは、交互に訪れるレム睡眠とノンレム睡眠のバランスがとれていて安定感があり、脳や身体がしっかりと休まった実感を感じられる状態と言えます。
睡眠の質は、目覚めの良さや、睡眠でしっかりと休息がとれていると感じられているかどうかで測ることができると考えられています。また、昼間の起きている時間帯の行動意欲や眠くならないかどうかなどでも評価される可能性が高いです。
睡眠の質が良い状態を目指すことは、心身ともに健全に暮らすために不可欠な要素のひとつと考えられています。
良い睡眠のためには「質」のみではなく、季節や年齢に合わせた適切な睡眠の「量」を確保することも必要だと言われています。
睡眠の質を上げる方法10選
睡眠の質を上げる方法として、以下の10個の方法を紹介していきます。
- 深呼吸をする
- 睡眠環境を整える
- 就寝前に入浴をする
- 起床時に日光を浴びる
- 就寝直前にご飯を食べない
- 生活習慣を整える
- 適度に運動を行う
- 就寝直前に電子機器を見ない
- 朝食を食べる
- ストレスを解消する
深呼吸をする
睡眠の質を上げる方法のひとつとして、深呼吸をするということが挙げられます。
自分では気付かないうちに、浅い呼吸になってしまっている人は多いと言われています。浅い呼吸だと交感神経が高まってしまい、心身を緊張状態にさせやすいです。
そこで深呼吸をすることで自律神経のバランスを整えられることが期待できます。
また、深呼吸をすることで副交感神経が優位となり、リラックス効果が得られて緊張がほぐれる可能性が高いです。
なお、深呼吸をする際、単純に酸素を深く肺に吸い込む胸式呼吸ではなく、お腹に酸素を取り込む腹式呼吸を意識することで疲れが癒されやすいと言えます。
深呼吸習慣化デバイス「ston s」

- 「ston s」は、エナジードリンクでも、電子タバコでもない深呼吸を習慣化することを目的としたデバイス
- 罪悪感0で瞬間リフレッシュが可能
- 充電の必要がなく、どこでも持ち運びできる
睡眠環境を整える
睡眠環境を整えることも、睡眠の質を上げる方法のひとつと言えます。
快適な温度、不安感を覚えない程度の暗さで、静かな環境であると、眠りやすい場合が多いです。
寝具やエアコンなどで季節に応じた適正な温度にすると、快適に眠れると考えられています。
例えば冬は寝る前に寝室を温めておくなど、寝ている間のみではなく寝る前の準備として環境を整えることも大切と言えます。
また明るい環境で眠ると途中で目が覚めてしまいやすくなるため、遮光カーテンや足元灯などを活用して寝ている間は部屋をできる限り暗くすることが有効である可能性が高いです。
それから、ラジオや音楽を聞きっぱなしにせずに静かな環境で眠ることも睡眠の質が上がりやすいです。
就寝前に入浴をする
睡眠の質を上げる方法のひとつには、就寝前に入浴をするということも挙げられます。
人の体内時計のリズムにより、夜間は身体を休めるために体温が低くなっていく傾向があります。そして、眠る前には急速に体温が下がり、眠気を強く感じやすいです。
この体温変化が円滑に行われると安眠効果が得られると言われています。
入浴によって一時的に身体を温めて体温を上げ、その後血管が拡張して熱が放出されやすくなり、体温が下がる傾向があります。体温が下がる時に眠気が強くなるため、就寝前に入浴することで就寝時に自然と眠気を感じて寝つきが良くなる可能性が高いです。
中でもぬるめのお湯にゆっくりとつかることで副交感神経が優位になり、リラックス効果もあるため、睡眠の質を上げることが期待できると言われています。
あまり高い温度のお湯では血流や心臓の働きなど身体に負担がかかり、また交感神経の働きが活性化して興奮状態になってしまうため注意が必要です。
起床時に日光を浴びる
起床時に日光を浴びることも睡眠の質を上げる方法のひとつと言われています。
起床時に日光を浴びることで体内時計がリセットされ、目から入った光の刺激が脳に伝わり、「セロトニン」という脳内物質が分泌される場合が多いです。この「セロトニン」は夜になると睡眠ホルモンと呼ばれている「メラトニン」に変わると考えられています。
つまり起床時に日光を浴びて「セロトニン」が作られていると、夜には「メラトニン」の分泌が増えて自然な眠気を感じ、睡眠の質が高まる可能性が高いです。
朝起きてからすぐに日光を浴びないと、少しずつ眠気を感じる時間帯が後ろにずれてしまい、生活のリズムが夜に偏ってしまう場合があります。
就寝直前にご飯を食べない
就寝直前にご飯を食べないことも、睡眠の質を上げる方法のひとつということができます。
就寝直前にご飯を食べると、就寝中も胃や腸は消化のために活発に働き続けることになり、睡眠の妨げとなりやすいです。
消化しにくい揚げ物などの脂質の多い食べ物は消化に時間がかかるため、食べる時間帯に注意が必要と言えます。
生活習慣を整える
睡眠の質を上げる方法のひとつに、生活習慣を整えるということも挙げられます。
人は体に備わっている体内時計に則って、生命活動を行っていると言われています。
朝の光を受けると体内時計がリセットされ、身体を1日24時間のリズムに合わせてくれる可能性が高いです。この体内時計のリズムに合わせて起きる時間を決め、生活習慣を整えれば、夜には自ずと眠るための体勢となって睡眠の質が上がる傾向があります。
休みの日などに普段より長めに寝たい場合でも、体内時計のリズムがズレすぎてしまわないよう、30分遅く起きる程度に留めておく方が良いでしょう。
適度に運動を行う
睡眠の質を上げる方法には、適度に運動を行うことも挙げられます。
人の深部体温は約24時間のリズムで変化しており、昼間に上がって夜寝る頃には下がりやすいです。
身体を動かすことで深部体温が上がって、身体全体の血の巡りが良くなり、熱が放出されやすくなることで深部体温が下がる傾向があります。体温が下がる時に眠気が強くなるため、この仕組みを活かすことで寝つきが良くなる可能性が高いです。
また、軽く身体を動かすことで睡眠が深くなり、熟睡度が増すと考えられています。
例えば、眠る3時間前までに軽いストレッチを行うと、副交感神経が優位となって精神的にも身体的にもリラックス状態になりやすいです。そのため、睡眠の質が高まる見込みがあります。
ただし、激しい運動は疲労物質が蓄積されて疲れてしまい、逆に睡眠の質を下げてしまう可能性があるため注意が必要と言えます。
就寝直前に電子機器を見ない
就寝直前に電子機器を見ないことも、睡眠の質を上げる方法のひとつと言えるでしょう。
電子機器の液晶画面からはブルーライトが発せられていると言われています。このブルーライトを浴びると脳が昼間と勘違いして覚醒し、寝つきが悪くなる可能性が高いです。
例えばスマートフォンやパソコンなどの液晶画面は就寝直前に見ない方が良いと考えられています。
朝食を食べる
朝食を食べることも、睡眠の質を上げる方法のうちのひとつと言えます。
朝食を食べることで体内時計がリセットされ、夜には自然と眠気が起きやすいです。また、朝食にトリプトファンを含む食べ物を摂取すると、夜に「睡眠ホルモン」と呼ばれる「メラトニン」の分泌が増えて眠りにつきやすくなると考えられています。
例えばトリプトファンを含むヨーグルトや、バナナなどを朝食に食べると睡眠の質を上げることにつながるでしょう。
ストレスを解消する
睡眠の質を上げる方法には、ストレスを解消することも挙げられます。
ストレスがあると交感神経が優位となり、脳が覚醒して眠りが浅くなり、睡眠の質が低くなりやすいです。
また、ストレスがあると、副腎皮質からストレスホルモンであるコルチゾールが分泌されると言われています。コルチゾールは体内時計を乱し、睡眠のリズムを崩して睡眠の質を下げる可能性が高いです。そのため、ストレスを解消することで睡眠の質が上がると言えます。
睡眠不足は日中の判断力や集中力の低下をもたらし、さらにストレスを引き起こすという悪循環に陥ってしまう可能性があるため注意が必要と言えます。
睡眠の質を上げることによるメリット
睡眠の質を上げることによるメリットには以下のようなことがあると言えます。
- 肌つやが改善する
- 疲労回復効果を得られる
- 健康状態を維持できる
- ストレスが緩和する
- 肥満になりにくくなる
肌つやが改善する
睡眠の質を上げることによるメリットには、肌つやを改善することが挙げられます。
寝入ってからすぐに訪れるノンレム睡眠時は成長ホルモンが分泌し、新陳代謝が活性化されてお肌のターンオーバーが促進される可能性が高いと言えます。
また、睡眠ホルモンと呼ばれているメラトニンの抗酸化作用で肌の老化を防止することが見込めます。
疲労回復効果を得られる
疲労回復効果を得られることは、睡眠の質を上げることによるメリットのひとつと言えます。
質の高い睡眠を取ることで交感神経と副交感神経のバランスが保たれ、脳内細胞もリラックス状態となって休息状態になると言われています。
これにより細胞の代謝が促進されて修復されるため、疲労回復効果が得られる可能性が高いです。
健康状態を維持できる
睡眠の質を上げることによるメリットのひとつとして、健康状態を維持できることが挙げられます。
睡眠の質が上がると生活のリズムが整いやすくなり、自律神経が整うため健康状態が維持できることが期待できます。また、代謝や免疫など身体の健康のみでなく、心の健康にもつながる可能性が高いです。
良質な睡眠が不足すると生活習慣病のリスクが高まると言われています。例えば眠りが浅い場合や、深夜まで起きている場合は、血圧が高い状態が維持されてしまい、高血圧になりやすいです。
また、質の良い睡眠が足りていない状態だとインスリンというホルモンの働きが悪くなるため、血糖値のコントロールが利かなくなり、糖尿病のリスクが高まる場合があります。
ストレスが緩和する
睡眠の質を上げることによるメリットには、ストレスが緩和するということも挙げられます。
睡眠の質を上げると、ストレスホルモンであるコルチゾールが副腎皮質から分泌される量が調整され、ストレスが緩和する効果が期待できます。
また質の良い睡眠で脳の疲れがとれると、記憶力や集中力が高まり、ストレスが緩和する可能性が高いと言えます。
肥満になりにくくなる
肥満になりにくくなることも、睡眠の質を上げることによるメリットと言えます。
睡眠が不足するとレプチンという食欲を抑制すると言われるホルモンが減少し、逆にグレリンという食欲を増進させるホルモンが増加すると考えられています。そのため、グレリンが増加すると疲れや眠さを解消させようと高脂肪、高カロリーの食べ物を欲するようになりやすいです。
質の高い睡眠をとることでこれらの食欲に関わるホルモンのバランスが整い、不要なエネルギーの摂取を控えるようになるため、肥満になりにくくなることが見込めます。
睡眠の質が下がってしまう原因
睡眠の質が下がってしまう原因は、主に以下のようなことが挙げられます。
- 精神的なストレス
- 睡眠環境の悪さ
- カフェインやアルコール
- 生活リズムの乱れ
精神的なストレス
精神的なストレスは、睡眠の質が下がってしまう原因のひとつと言えます。
精神的なストレスを感じていると交感神経が優位な状態になり、自律神経のバランスが崩れると考えられています。そうすると脳が覚醒した状態が続き、睡眠の質が下がってしまう可能性が高くなるでしょう。
睡眠環境の悪さ
睡眠の質が下がってしまう原因のひとつとして、睡眠環境の悪さがあると言えます。
眠りやすい環境が整っていないと寝つきが悪くなってしまったり、眠りが浅くなってしまったりするなど睡眠の質が下がってしまう場合が多いです。快適な温度、明るすぎない照明で、静かな環境が、眠りやすいと考えられています。
例えば、寝具やエアコンの温度が季節や寝室にあっていないと睡眠の質が下がってしまう可能性が高いです。
また明るすぎる環境で眠ると途中で目が覚めてしまったり、深く眠れないケースもあります。
それから、騒音が気になるような環境で眠ることも睡眠の質が下がってしまいやすいです。
その他、マットレスのスプリングの具合が合っていない、枕の形が合っていないなど寝具の問題でも睡眠の質が下がってしまうことが考えられます。
カフェインやアルコール
カフェインやアルコールも睡眠の質が下がってしまう原因と考えられています。
カフェインには覚醒作用があると考えられているため、寝る前に摂取すると寝つきが悪くなるなど、睡眠の質を下げてしまう可能性が高いです。
アルコールは早く寝るためには効果を発揮しますが、レム睡眠が減って眠りが浅くなってしまうと言われています。また、アルコールは睡眠のリズムを不安定にして、眠りの質を低下させやすいです。
生活リズムの乱れ
生活リズムの乱れも、睡眠の質が下がってしまう原因のひとつと言われています。
夜遅くまで起きていて生活リズムが乱れると体内時計が狂い、寝つきが悪くなったり、途中で目が覚めてしまうなど、睡眠の質が下がってしまう可能性が高いです。
また起きる時間が遅く日光を浴びるタイミングが遅くなるのも、体内時計のズレに繋がり、睡眠の質が下がってしまう場合があります。
睡眠の質が低いことによる心身への影響
睡眠の質が低いことによる心身への影響には、以下のようなことがあると考えられています。
- 生活習慣病になる恐れがある
- 集中力や注意力が低下する
- 精神的に不安定になる
生活習慣病になる恐れがある
睡眠の質が低いと、生活習慣病になる恐れがあります。
生活習慣病とは「食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣が、その発症・進行に関与する疾患群」と厚生労働省の資料に定義されていると言われています。
生活習慣病には以下のような病気が挙げられます。
- がん
- 心筋梗塞
- 糖尿病
- 高血圧 など
睡眠の質が低いとホルモンバランスが変化し、代謝や食欲に影響を及ぼすため、生活習慣病になりやすいと言えます。
例えば、質の良い睡眠が足りていない状態だとインスリンというホルモンの働きが活発ではなくなるため、血糖値のコントロールが利かなくなり、糖尿病を発症する恐れが高まる場合があります。
また眠りが浅い場合や、深夜まで起きていると血圧が高い状態が維持されてしまい、高血圧になりやすいと言われています。
集中力や注意力が低下する
睡眠の質が低いことで、集中力や注意力が低下すると言われています。
睡眠の質が低いと脳が必要な休息をとれていない状態となり、脳の働きが悪くなることで集中力や注意力が低下すると考えられています。
睡眠の質が低い状態で運転などをすると、判断が遅れることから事故につながる可能性があるため注意が必要でしょう。
精神的に不安定になる
睡眠の質が低いことによる心身への影響のひとつとして、精神的に不安定になることが挙げられます。
睡眠の質が低いと脳の感情をつかさどる部分が不活性となり、ストレスホルモンが増えて精神的に不安定になると言われています。
また、寝ている間に悲しみや怒りなどのマイナスの感情を整理してストレスを緩和するため、睡眠の質が低いと、ストレスが緩和されず精神的に不安定になる可能性が高いです。
精神的に不安定な状態が続くとうつ病になるリスクも高まるため、注意が必要と言えます。
睡眠の質をセルフチェックする方法
睡眠の質をセルフチェックする方法として、次のようなチェック項目に当てはまるか否かを確認する方法があると言えます。
- 日によって睡眠時間がまちまちである
- 睡眠中にピクピク足が動く
- 寝相が悪く、大きな声で寝言を言う
- 毎夜途中で目が覚めてしまう
- 深く眠れていない感じがする
- スッキリと目覚められない
- 悪い夢を見ることがある
- 大きないびきをかく
- 身体の痛さやかゆみ、息苦しさ、咳などがあり眠れない
- 日中強い眠気があったり、居眠りしてしまうことがある
途中で目が覚めてしまうことなく、必要な睡眠時間が確保できているかで睡眠の質をチェックすることができると考えられています。
また、大きな声で寝言を言ったり、悪い夢を見るなど、眠りが浅くないかどうかで睡眠の質をチェックできる可能性が高いです。
そのほかにも、朝スッキリと目覚められるか、昼間に強い眠気がないかなど、熟睡度でも睡眠の質をチェックできる場合があります。
睡眠の質を上げることに関するよくある質問
睡眠はどのようなメカニズムですか?
睡眠は浅い眠りである「レム睡眠」と、深い眠りである「ノンレム睡眠」が交互に繰り返されていると言われています。
「レム睡眠」は身体を休ませる睡眠であり、脳は活発に働いて記憶の整理などが行われていると考えられています。「ノンレム睡眠」は交感神経や脳も休ませる睡眠で、脳の疲れをとるために必要である場合が多いです。
眠り始めるとまず深い眠りである「ノンレム睡眠」に入り、1時間ほどで段々と眠りが浅くなっていき、「レム睡眠」へ移ると言われています。
その後、1サイクル約90分で「ノンレム睡眠」と「レム睡眠」が交互に現れ、起きるまでに3~5回程度繰り返される場合が多いです。
睡眠の質を上げる飲み物や食べ物はありますか?
飲み物はハーブティーや白湯、ホットミルクなどが睡眠の質を上げると言われています。
ハーブティーは種類によってリラックス効果を得られるため、睡眠の質を上げる効果が見込めます。
白湯は身体を冷やすことなく水分補給ができるため、睡眠の妨げとならない場合が多いです。
また、ミルクにはリラックス成分であるセロトニンのもとになるトリプトファンが含まれており、入眠を促す働きがあると考えられています。
食べ物は納豆や豆腐などの大豆製品、卵やまぐろなどのたんぱく源となるもの、バナナなどが睡眠の質を上げやすいでしょう。
大豆製品やたんぱく源となる食物、バナナなどにもトリプトファンが多く含まれているため、これらを食べることで、セロトニンを作り出し、睡眠の質が上がると言われています。
寝不足な人の特徴は?
寝不足な人には以下のような特徴があると言えます。
- 日中、強烈な眠気に襲われる
- 気力がなく、モチベーションが低い
- 吐き気や頭痛などの体調不良が続いている
本来寝ている間に脳や身体が回復するところ、寝不足の場合はしっかりと回復できない場合が多いです。そうすると疲れが取れず、日中にひどく眠くなったり、精神的にも気力がなく、やる気が起きない状態になることがあります。
また、寝不足で自律神経のバランスが崩れると吐き気がしたり、脳の疲労がとれず、脳の酸欠状態が続いていると頭痛がしたりする場合があります。
【監修者プロフィール】

江東こころのクリニック院長
谷本 幸多朗医師
九州大学医学部卒業後、帯広第一病院にて救急医療や外科及び内科の研修を経験する。
2013年より久喜すずのき病院にて精神科急性期医療を後期研修し精神保健指定医となる。
2018年より江東区にて一般メンタルクリニックに加えて認知症デイケアを併設した物忘れ外来も行う精神科クリニックである江東こころのクリニックを開業し、現在に至る。
▼主な経験
・精神保健指定医の経験あり
・製薬会社主催の各講演会や地域の医療職対象の勉強会において講演や座長の経験多数あり