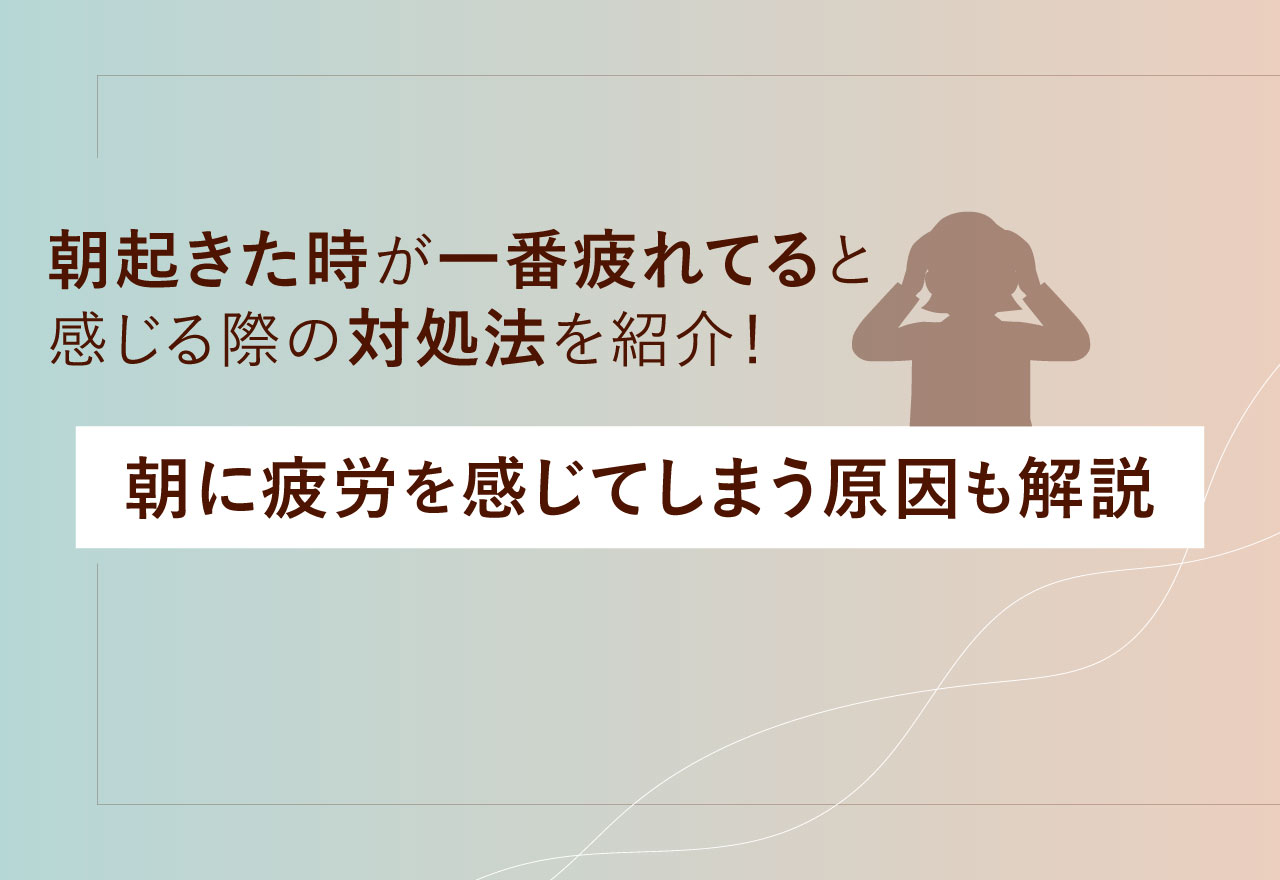目次
朝起きた時が一番疲れてると感じる際の対処法
朝起きた時が一番疲れていると感じる際の対処法は、主に以下の7つが挙げられます。
- 睡眠の質を上げる
- 深呼吸をする
- 生活リズムを整える
- 朝食を食べる
- 運動をする
- 日光浴をする
- 目覚ましの音を優しい音に設定する
睡眠の質を上げる
朝起きた時が一番疲れていると感じる人は、睡眠の質を上げると良いでしょう。
ここで言う睡眠の質を上げるとは、睡眠時間の確保のみでなく、眠る前の行動や環境を整えることなどが含まれます。
睡眠の質が低いと自律神経のバランスが崩れ、効果的な休息が取れず、朝起きた時に疲れを感じてしまう可能性が高いです。
なお、主に以下の方法で、睡眠の質を上げる効果を得られると言われています。
- 肌触りの良い寝具に変える
- 入浴は就寝の1〜2時間前にする
- ぬるめの浴槽に10〜20分浸かる
- 寝る予定の2時間前からテレビやスマホの使用を控える
- 寝る予定の3時間前までに夕食を済ませる
- 眠る前は部屋の明かりを暗めにしておく
- カフェインやアルコールの摂取は3時間前までにする
- 6〜8時間の睡眠時間を確保する など
また、寝すぎることも起きた時の疲労感に繋がると考えられているため、注意しましょう。
深呼吸をする
朝起きた時に疲労を感じた際には、深呼吸をすることも1つの対処法だと言えます。
深呼吸とは一般的に、鼻からゆっくりと息を吸い込み、口からゆっくりと息を吐き出す呼吸の方法のことを指します。
朝起きた時に疲れを感じるのは、睡眠中に交感神経が優位になり、効果的な休息が取れていないことが原因の一つと考えられます。 そこで、深呼吸をすることで自律神経のバランスを整え、心身をリラックスした状態に導くことができると言われています。
具体的には、鼻からゆっくりと息を吸い込み、口からゆっくりと息を吐き出す動作を数回繰り返すことで、自律神経のバランスが整い、起床時の疲労感を和らげることができる場合が多いです。
また、深呼吸を行う際は、無理のないように行い、もし苦しさを感じた時は中断するようにしましょう。
深呼吸習慣化デバイス「ston s」

- 「ston s」は、エナジードリンクでも、電子タバコでもない深呼吸を習慣化することを目的としたデバイス
- 罪悪感0で瞬間リフレッシュが可能
- 充電の必要がなく、どこでも持ち運びできる
生活リズムを整える
朝起きた時が一番疲れていると感じる人は、生活リズムを整えることで改善できる場合があります。
生活リズムが乱れると、睡眠ホルモンやストレスホルモンの分泌が不安定になり、朝の疲労感につながるケースが多いです。
生活リズムを整えるためには、以下のような習慣が有効であると考えられています。
- 食事時間を固定する
- 起床時に太陽の光を浴びる
- 毎日同じ時間に寝る
- 毎日同じ時間に起きる
- 適度に運動をする など
なお、休日に深夜まで夜ふかしをしたり朝寝坊をしたりしてしまうと、平日の生活リズムが乱れ、朝の疲労を感じやすくなると考えられているため、注意しましょう。
朝食を食べる
起床時に一番疲れを感じる場合には、朝食を食べることで改善できる可能性があります。
睡眠中は長時間エネルギーを補給できないため、起床時に血糖値が下がっていたり、栄養が不足していたりすることが多いです。その結果として、朝起きた時に疲れを感じる場合が多くなると考えられています。
そのため、朝食を摂取することで日中の血糖値を安定させ、エネルギー供給をスムーズにすることにより、日中の疲労感を軽減できると言われています。
ちなみに、朝食は起きて1時間以内に食べるようにすると良いでしょう。インスリンの働きが活発となり、血糖値の乱高下を防いでくれる可能性があります。
また、朝食は炭水化物のみでなく、タンパク質を多く含む食べ物や野菜、果物、乳製品なども食べると良いと言われています。
運動をする
起きた時が一番疲れている場合の対処法の一つに、運動をするという方法が挙げられます。
適度に運動することで血流が促進され、筋肉や神経の働きを活性化させることができる場合が多いです。
睡眠中は副交感神経が優位になり、血流が滞りやすいため、起床後にだるさや疲労感を感じやすくなると考えられます。そこで、運動することによって交感神経を活性化させることで、朝の疲労感を軽減できると言えるでしょう。
朝起きた時の疲れへの対処法として、主に以下の運動が効果的だと言えます。
- ストレッチ
- 散歩
- スクワット
- ヨガ
- ラジオ体操 など
なお、過度の運動はかえって疲労がたまりやすくなるため、無理なく続けられる強度の運動を意識すると良いでしょう。
日光浴をする
起きた時が一番疲れている場合には、日光浴をすると良いと考えられています。
朝起きた時に疲れを感じるのは、睡眠の質が低下していたり、体内時計が乱れていたりすることが原因と考えられています。
そこで日光を浴びることで、睡眠ホルモンである「メラトニン」の分泌リズムが整い、夜間の睡眠の質が向上するため、翌朝の疲労感が軽減しやすくなるでしょう。
なお、起床したら1時間以内に日光を浴びると良いでしょう。また、日光を浴びられるように、窓際で15分程度朝食を摂ると良いと考えられています。
しかし、夏は朝の日差しが強く、起きてすぐにカーテンを全部開いてしまうと不快に感じる場合があります。そのため、日差しが強い日にはカーテンを徐々に開けるなど無理のない範囲で工夫が必要だと言えるでしょう。
目覚ましの音を優しい音に設定する
朝起きた時に疲れていると感じる場合は、目覚ましの音を優しい音に設定してみると疲労感が和らぐ可能性があります。
大音量や刺激の強い目覚まし音は交感神経を活性化させ、ストレスホルモンである「コルチゾール」が過剰分泌されてしまうと考えられています。その影響で、朝起きた時に強い疲労を感じてしまう場合が多いです。
具体的に目覚ましの音は、小さな音から徐々に音量が上がるタイプの音や、波の音などの自然音が良いと言われています。
しかし、今まで大きい音を目覚まし音にしていた人が、急に自然音などの優しい音に目覚まし音を変えてしまうと、起きられなくなる可能性が少なくないです。
そのため、目覚ましの音を変更するタイミングは、休日から試してみたり、家族の協力を得たりなどの工夫が必要だと言えます。
朝起きた時が一番疲れてると感じる原因
朝起きた時が一番疲れてると感じる原因は、主に以下の3つだと考えられています。
- 自律神経の乱れ
- エネルギーの不足
- 睡眠を阻害する病気
自律神経の乱れ
朝起きた時に疲れを感じる原因として、自律神経の乱れが関係している可能性が少なくないです。
自律神経とは、心拍や消化、体温などを無意識に制御する神経で、交感神経と副交感神経という2つの神経に分けられます。
通常、夜は副交感神経が優位になり、朝になると交感神経が活性化して目が覚める仕組みになっていると言われています。
しかし、自律神経が乱れると、この交感神経と副交感神経の切り替えが上手くできず、朝起きても体が覚醒しないため、疲れを感じやすくなる場合が多いです。
また、仕事や人間関係のストレスが過剰になると、自律神経が乱れやすいと言われています。
他にも、カフェインの過剰摂取や寝る直前のスマホの使用によって、交感神経が刺激され続けてしまい、自律神経の乱れに繋がるとも考えられています。
もし自律神経の乱れが原因で慢性的な倦怠感が続いている場合には、医療機関に相談することも検討すると良いでしょう。
エネルギーの不足
朝起きた時に強い疲労を感じる原因として、エネルギー不足が考えられます。
ここで言うエネルギー不足とは、体が活動するために必要なエネルギーが供給されず、脳や筋肉が機能しない状態を指します。
睡眠中は長時間エネルギーの補給ができないにもかかわらず、呼吸や代謝によってエネルギーが消費されるため、朝起きる頃には血糖値が下がり、脳や筋肉に必要なエネルギーが足りなくなっている場合があります。
そのため、夜ご飯を抜いたり軽い食事のみにした翌朝は、強い疲れを感じるケースが少なくないです。
食事は、単にエネルギーを補うだけでなく、栄養バランスを考えて摂取することが大切です。
また、たんぱく質やビタミンB群はエネルギー代謝を助ける役割があるため、不足しないよう意識して取り入れるようにしましょう。
睡眠を阻害する病気
朝起きた時が一番疲れてると感じるのは、睡眠を阻害する病気が原因である可能性があります。
ここで言う睡眠を阻害する病気とは、眠りの質が低下したり、途中で何度も目が覚めたりすることで、休息を取りにくくなる疾患のことを指します。
もし睡眠がしっかり取れていないと、脳や身体の回復が妨げられ、結果として朝の疲労感につながると考えられています。
睡眠を阻害する病気には、主に以下のようなものがあります。
- 貧血
- 自律神経失調症
- 睡眠時無呼吸症候群
- うつ病
- ナルコレプシー
- むずむず脚症候群(レストレスレッグズ症候群)
- 概日リズム睡眠障
- 甲状腺疾患
もし朝起きた時に強い疲れを感じる状態が続いており、その他の症状がある場合には、医療機関に相談することを検討すると良いでしょう。
朝起きた時に疲れを感じやすい睡眠前の行動
朝起きた時に疲れを感じやすくなる睡眠前の行動として、主に以下の4つの行動が挙げられます。
- カフェインが入った飲み物を飲む
- 電子機器を見る
- 食べ物を食べる
- 入浴をする
カフェインが入った飲み物を飲む
寝る前にカフェインを摂取すると、睡眠の質が低下し、朝起きた時に疲れを感じやすくなる可能性があります。
カフェインは、覚醒作用や興奮作用を持ち、眠気を抑えてしまう効果があると考えられています。
一般的に、カフェインの効果は摂取後30分〜1時間でピークを迎え、体内から完全に排出されるまでに4〜6時間かかる場合が多いです。
また、カフェインには中枢神経を刺激し、交感神経を活性化させる作用があるため、摂取すると脳が覚醒し、寝つきが悪くなる可能性が高いです。そのため、夕食後にコーヒーを飲んだら、寝付きが悪くなってしまったケースがよく見受けられます。
ただしカフェインの影響度合いには個人差があり、例えばカフェインの分解が遅い人は、夕方に摂取しても睡眠の質が下がってしまう可能性があるため注意が必要です。
電子機器を見る
寝る前にスマホやパソコンなどの電子機器を見ると、睡眠の質が低下し、朝起きた時に疲れを感じやすくなる可能性があります。
電子機器の画面から発せられるブルーライトには、脳を覚醒させる作用があり、睡眠を促すホルモンである「メラトニン」の分泌を抑制する可能性があると考えられています。
そのため、寝る直前までスマホを見ていると、ベッドに入ってもなかなか眠れない場合が多いです。また、睡眠時間や睡眠の質が低下すると、脳や体の疲労が回復できず朝の疲労感が残りやすくなる場合があります。
もし寝る前にどうしても電子機器を使用したい場合は、ブルーライトカットのメガネやフィルターを活用すると良いでしょう。
食べ物を食べる
寝る前に食べ物を食べると、朝起きた時に疲れを感じる原因になると言われています。
入眠の1〜2時間前の食事をしてしまい消化が終わらないまま寝ると、内臓が休まらず、深い眠りが妨げられる可能性が高いです。
その結果として、寝ている間に心身の回復ができず、朝起きた時に疲労感を感じやすくなるケースがあります。
そのため、寝る3時間前までには食事を済ませると良いでしょう。また、寝る3時間前の食事であっても、脂っこい食べ物や過剰な量の食事は朝に疲れを生じさせる場合があるため、注意が必要だと言えます。
入浴をする
寝る直前に入浴をすると、朝起きた時に疲れを感じる原因になると考えられています。
入眠の1時間前など寝る直前に熱いお風呂に入ると、交感神経が活性化されてしまい、寝つきが悪くなる可能性が高まると言われています。
その結果、翌朝に「体が重い」「熟睡できなかった」と感じる人が多いと言えます。なお、入浴は寝る予定の2〜3時間前に入ると睡眠に良い影響があると言われています。
また、お風呂のお湯の温度は38〜41℃で、10〜20分程度湯船に浸かると良いでしょう。体温が自然に下がることで寝つきがよくなり、翌朝の疲労感を軽減できると考えられています。
朝起きた時が一番疲れてることに関連するよくある質問
朝起きた時が一番疲れてるのはうつ病ですか?
朝起きた時に強い疲労を感じるからといって、必ずしもうつ病とは限りません。
睡眠不足や生活習慣の乱れ、ストレス、栄養不足などが原因となって、同様の症状が起こることがあります。
ただし、朝の疲労感が長期間続き、気分の落ち込みや興味・意欲の低下などが伴う場合は、うつ病の可能性も考えられるため、注意が必要です。
睡眠の質を上げる方法はありますか?
睡眠の質を上げるには、寝る前の行動や睡眠の環境を改善し、体内リズムを整えることが重要であると考えられています。
具体的には、以下の5つの方法が睡眠の質を上げるのに有効だと言われています。
- 適度な運動を取り入れる
- 食事とカフェインの摂取に気をつける
- 寝室の環境を整える
- 寝る前にリラックスする習慣をつける
- 規則正しい生活リズムを心がける
疲労が溜まっているとはどのような状態ですか?
疲労が溜まっている状態とは、体や脳が回復できず、倦怠感や集中力の低下が続いている状態のことを指すと言えます。
疲労は、体の筋肉の疲れ、心の疲れ、自律神経の乱れによる疲れの3つに大きく分けられると考えられています。疲労が溜まっている状態が続くと、体調不良に繋がる可能性が高いと言えるでしょう。
具体的に疲労が溜まっている体のサインとして、主に以下のような自覚症状が挙げられます。
- 朝起きても疲れている感覚がある
- 思考力が低下し、判断ミスが増える
- 刺激への反応が鈍くなる
- 注意力が続かず、集中できなくなる
- 動作が遅くなり、作業効率が落ちる
- 行動量が減り、やる気が出にくくなる
- イライラしたり、感情的になりやすくなる
- 頭痛が続きやすくなる
- 肩こりや腰痛が悪化する
- 目がかすみやすくなる など
これらの症状が続く場合、疲労が蓄積されている可能性があります。もし休息をとっても症状が改善されない場合には、医療機関へ相談すると良いでしょう。
【監修者プロフィール】

江東こころのクリニック院長
谷本 幸多朗医師
九州大学医学部卒業後、帯広第一病院にて救急医療や外科及び内科の研修を経験する。
2013年より久喜すずのき病院にて精神科急性期医療を後期研修し精神保健指定医となる。
2018年より江東区にて一般メンタルクリニックに加えて認知症デイケアを併設した物忘れ外来も行う精神科クリニックである江東こころのクリニックを開業し、現在に至る。
▼主な経験
・精神保健指定医の経験あり
・製薬会社主催の各講演会や地域の医療職対象の勉強会において講演や座長の経験多数あり