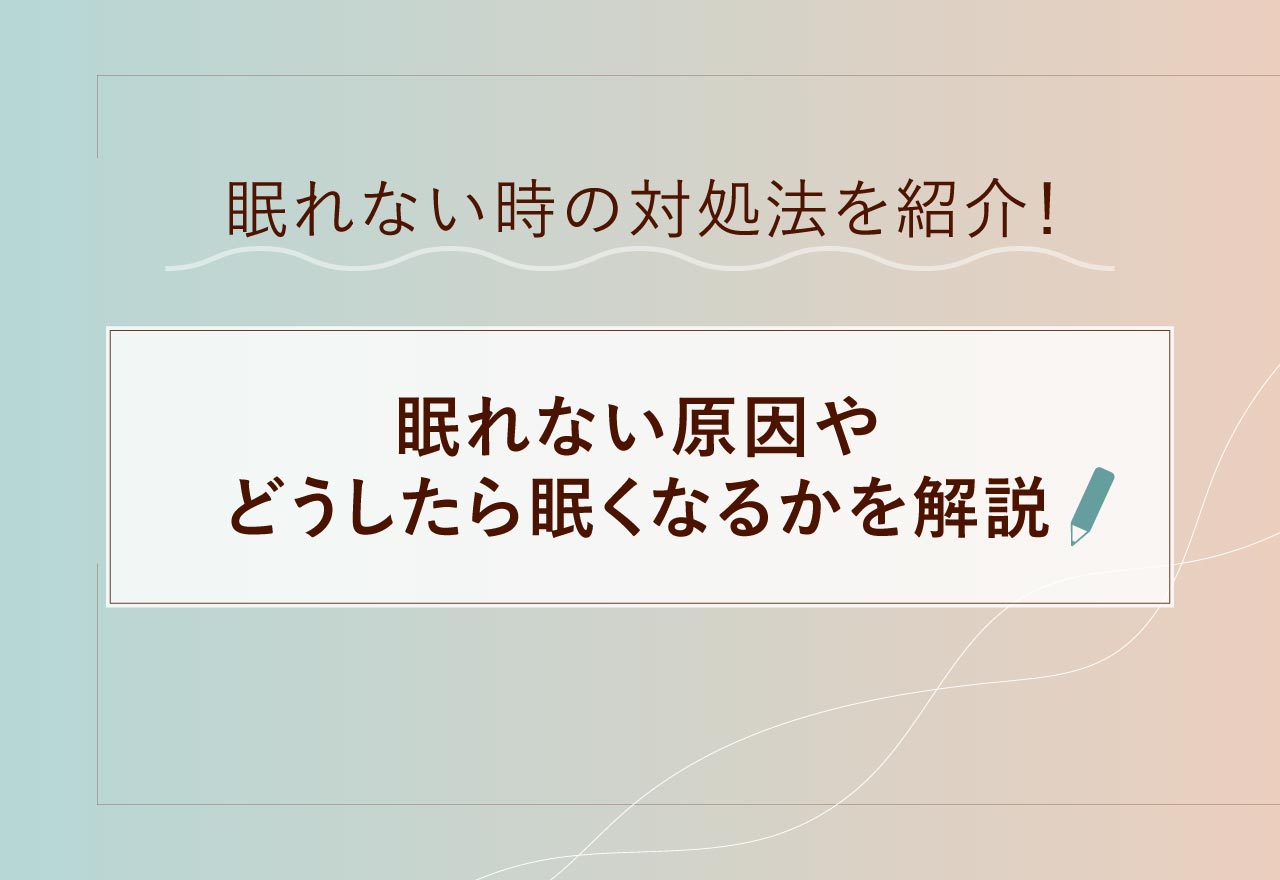目次
眠れない時の対処法
眠れない時の対処法は、以下の通りです。
- 深呼吸をして落ち着く
- 入浴をして身体を温める
- 好きな香りをかぐ
- ゆっくりストレッチをする
- ツボを押す
- 悩みを紙に書き出す
- 温かい飲み物を飲む
深呼吸をして落ち着く
眠れないときの対処法の1つとして挙げられるのが、深呼吸によって心を落ち着けることです。
深呼吸を行うと、副交感神経が優位になりやすくなります。その結果、交感神経の働きが抑えられ、心拍数の上昇や緊張感の発生も抑えられやすくなるでしょう。
また、副交感神経が優位な状態では眠気が生じやすいとされており、スムーズに睡眠へ移行できる可能性が高いと言えます。
深呼吸習慣化デバイス「ston s」

- 「ston s」は、エナジードリンクでも、電子タバコでもない深呼吸を習慣化することを目的としたデバイス
- 罪悪感0で瞬間リフレッシュが可能
- 充電の必要がなく、どこでも持ち運びできる
入浴をして身体を温める
入浴によって身体を温めることで、眠れない状態を改善できる可能性があります。これは、人間の身体が体温の低下によって眠気を感じやすくなるとされているためです。
そのため、入浴によって一時的に体温が上昇した後、平常の体温に戻る過程で眠気が誘発されることが期待されます。
また、入浴のタイミングは、就寝の1〜2時間前が効果的とされています。お湯の温度は38〜40℃程度、入浴時間は10〜30分程度が目安にすると良いでしょう。
なお、お湯が熱すぎると体温が過剰に上昇し、体が冷えるまでに時間がかかるため、かえって寝つきが悪くなることもあるため、注意が必要です。
好きな香りをかぐ
好きな香りをかぐことも、眠れないときの対処法の1つです。
人間の脳と嗅覚は密接に関係しているとされています。自分の好きな香りをかぐことで脳に直接作用し、副交感神経が優位になってリラックスした状態へ移行しやすくなります。
結果、心身が落ち着くことで質の高い睡眠が得られやすく、眠れないときの有効な対処法となる可能性が高いと言えます。
ゆっくりストレッチをする
眠れないときは、ゆっくりとストレッチをすることが有効だと考えられています。ここで言うゆったりとしたストレッチとは、反動をつけずに筋肉や関節を無理なく動かすことを指します。
筋肉や関節を伸ばすことで、身体が柔らかくなったり、緊張がほぐれたりする傾向があります。こうした働きにより、心拍数や血圧が安定し、副交感神経が優位になる効果も期待できるでしょう。
ツボを押す
特定のツボを押すことは、眠れない状態を改善するのに役立つことが多いと言えます。
ツボは特定の器官や臓器などとつながっているとされており、刺激することで対応する部位に作用する効果が期待されます。
そのため、身体の不調の原因となっているツボを刺激することで、症状が緩和され、眠りにつきやすくなる可能性があります。
悩みを紙に書き出す
悩みを紙に書き出す「ジャーナリング」という方法も、眠れないときの有効な対処法の1つです。
ジャーナリングとは、思考や感情を言語化して書き出す手法です。瞑想の一種とされ、気持ちの整理に役立つとされています。
自身の思考や感情を文字にすることで、心の中で考え続けることによる心理的な負担を軽減できる場合が多くあります。さらに、思考や感情が目に見える形になることで、何らかの発見や気づきを得るきっかけにもなりやすいでしょう。
ただし、時間をかけて深く考えすぎたり、自分の内面を無理に見つめようとしたりすると、かえって心理的な負担が大きくなり、逆効果になる可能性もあります。
無意識に浮かんだ考えや、重要度は低くても気になっていることなどに焦点を当て、軽い気持ちで書き出すようにすると良いでしょう。
温かい飲み物を飲む
温かい飲み物を摂取することで、眠りやすくなる可能性が高いです。一般的に睡眠前に身体が温まっていると、睡眠中に深部体温がより大きく低下しやすくなると考えられています。
そのため、深部体温の低下幅が大きいほど、睡眠の質が良くなりやすいと言えます。また、温かい飲み物は身体の内側から体温を上げるため、基礎代謝が高まり、自律神経のバランスも整いやすくなります。その結果、自然に眠気を感じやすくなることが期待できるでしょう。
眠れない時に考えられる原因
眠れない時に考えられる原因として、以下のような内容が挙げられます。
- 乱れた生活習慣
- 過度なストレス
- 乱れた睡眠環境
- カフェインやアルコールのとりすぎ
- 心身の病気
乱れた生活習慣
生活習慣が乱れていると、スムーズに眠れなくなることが多いです。人間の身体は、約24時間のサイクルで一周する体内時計を基準として、睡眠と覚醒のリズムを調節しています。そのため、生活習慣が乱れると体内時計のサイクルが崩れやすくなり、睡眠に支障をきたすことが少なくありません。
スムーズな睡眠を妨げる原因になりやすい生活習慣は、以下の通りです。
- 食事を取る時間が不規則になっている
- パソコンやスマホを長時間使用している
- 起床時間や睡眠時間の昼夜逆転している
- 睡眠時間が足りないまま起床してしまっている
- 就寝直前まで明るい空間で過ごしている
過度なストレス
過度なストレスも、眠れない原因の1つとなっている場合があります。ストレスを感じている状態では交感神経が優位になりやすく、脳が覚醒して目が覚めやすくなります。
その結果、心身が休息モードに入りにくくなり、眠れなくなることも少なくありません。また、ストレスは脳内の睡眠ホルモンの分泌を乱す原因にもなり、スムーズな入眠を妨げる要因となる可能性が高いと言えます。
乱れた睡眠環境
乱れた睡眠環境は、スムーズな入眠を妨げる要因になり得ます。入眠のしやすさや睡眠の質は、寝る環境の状況に大きく左右されやすいです。
例えば、昼光色の照明で部屋が明るいと、脳が覚醒しやすくなり、入眠しにくくなると考えられています。
そのほかにも、マットレスの硬さや枕の高さが合っていない場合、身体が休息モードに入りづらくなり、睡眠の質が低下しやすくなると言えるでしょう。
カフェインやアルコールのとりすぎ
カフェインやアルコールを過剰に摂取すると、眠れなくなる可能性が高いと言えます。これらは、脳を刺激して覚醒を促す作用があるとされています。
その結果、寝つきが悪くなり、眠れなくなることがあります。アルコールは、飲むと寝つきが良くなると思われがちですが、実際には深い睡眠が妨げられ、結果的に睡眠の質が低下してしまうことが多いと考えられています。
心身の病気
心身の病気が原因で眠れなくなることも少なくありません。不安障害やうつ病などの精神的な疾患では、不眠が症状の一つとして現れる傾向があります。また、身体の病気によって慢性的な痛みやかゆみが生じている場合も、眠れない状態に陥りやすいです。
眠れない原因となる代表的な心身の病気には、以下のようなものがあります。
- 不安障害
- うつ病
- 更年期障害
- 自律神経失調症
- 概日リズム睡眠障害
- 睡眠時無呼吸症候群
- レストレスレッグス症候群
眠れない時にとるべきでない行動
眠れない時にとるべきでない行動として、以下のような内容が挙げられます。
- 就寝直前に食事をする
- 就寝直前に入浴をする
- 電子機器を見る
就寝直前に食事をする
眠れないときに避けるべき行動の1つが、就寝直前の食事です。食事をすると、「レプチン」と呼ばれる満腹ホルモンの影響で眠気が生じやすいと言われています。
しかし、実際にはレプチンは消化を促進する役割を持ち、胃腸の働きを活発にする傾向があります。そのため、胃腸が活発に動いている状態で眠ると、結果的に睡眠の質が低下する可能性が高いです。
一般的に、食後に胃腸の働きが落ち着くまでの目安は約3時間とされており、就寝の3時間前までに食事を済ませることが望ましいと考えられています。
就寝直前に入浴をする
就寝直前の入浴も、眠れないときに避けるべき行動の1つとされています。
入浴直後は体温が上昇しているため、かえって眠気が覚めてしまうことが多いと言われています。また、お湯の温度が高すぎると身体が過剰に温まり、スムーズな入眠を妨げやすくなります。
そのため、就寝直前の入浴はなるべく避けるようにすると良いでしょう。
電子機器を見る
電子機器を見る行為は、睡眠を妨げる原因となる可能性が高いです。
スマートフォンやパソコンなどから発せられるブルーライトは、眠気を覚まさせる要因の1つとされています。
これは、ブルーライトによって脳が明るさを感じると、眠気を誘発するホルモン「メラトニン」の分泌が抑制されてしまうためです。
眠りにつきやすくなる習慣
眠りにつきやすくなる習慣として、以下のような物が挙げられます。
- 毎朝同じ時間に起きる
- 起床後に日光を浴びる
- 嗜好品を控える
- 適度な運動を習慣にする
- 入眠に役立つ栄養をとる
- 寝室の環境を整える
- 生活リズムを整える
毎朝同じ時間に起きる
毎朝同じ時間に起きることは、入眠しやすくなる習慣づくりに役立つとされています。起床時間を一定に保つことで、睡眠リズムが整い、入眠しやすくなる可能性が高まります。
これは、体内時計の乱れを防ぎ、一定のリズムを維持するのに効果的なためです。また、毎朝起きて日光を浴びることも、体内時計を整える有効な手段の一つとされています。
体内時計のリズムを崩さないためには、たとえ就寝時間が遅くなったとしても、起床時間はできるだけ変えないほうが望ましいでしょう。どうしても睡眠時間が不足する場合でも、起床時間のズレは1〜2時間以内にとどめるのが良いとされています。
起床後に日光を浴びる
眠りにつきやすくなる習慣の1つとして挙げられるのが、起床後に日光を浴びることです。
人間の身体は日光を浴びることで体内時計が整えられるとされており、日光を浴びてから約14〜16時間後に眠気が生じる傾向があります。
そのため、起床後に日光を浴びるように習慣付けるようにすると良いでしょう。
嗜好品を控える
眠りにつきやすくなる習慣づくりには、嗜好品を控えることも大切だと言えるでしょう。入眠を妨げる可能性があるものとしては、アルコールやカフェインなどが挙げられます。
アルコールは、摂取すると一時的に入眠しやすくなるとされていますが、代謝される過程で脳が覚醒しやすくなる傾向があります。その結果、深い睡眠が妨げられ、睡眠リズムが乱れる原因にもなりかねません。
一方、カフェインは中枢神経に作用し、眠気を覚まさせる効果があるとされています。また、カフェインの半減期は約3〜7時間とされているため、就寝に近い時間帯での摂取は避けたほうが良いでしょう。
適度な運動を習慣にする
適度な運動を習慣づけることで、入眠しやすくなる生活リズムを作ることにつながる場合があります。適度な運動には、睡眠の質を高めたり、スムーズな入眠を促したりする効果が期待できます。
睡眠の質が向上すると、心身の疲労やストレスが軽減されやすくなり、運動を続けるための体力を維持するのにも役立つでしょう。
ただし、運動によって一時的に眠気が覚めてしまう傾向もあります。入眠を妨げないためには、就寝の1〜2時間前までに運動を終えておくのが望ましいと言えるでしょう。
入眠に役立つ栄養をとる
眠りにつきやすくなる習慣のひとつとして、入眠に役立つ栄養素を摂取することが挙げられます。入眠をサポートする栄養素にはさまざまな種類がありますが、代表的なものにはグリシンやトリプトファンが知られています。
グリシンには深部体温を下げる働きがあるとされており、スムーズな入眠を促す効果が期待できるでしょう。
トリプトファンは、神経伝達物質であるセロトニンのもととなるアミノ酸です。セロトニンは、やがて睡眠ホルモンであるメラトニンへと変化するとされています。
寝室の環境を整える
寝室の環境を整えることも、眠りにつきやすくなる習慣づくりの一環です。寝室の環境は、入眠のしやすさを左右する重要な要素とされています。
空間に関する要素で重要なのは、照明の明るさ、室温、音などと言われています。そのほか、寝具や寝間着といった睡眠に関わるアイテムも重要であると考えられています。
寝室の環境を整える際の目安は、以下の通りです。
- 光度:真っ暗、暖色系の光
- 室温:20~26°C
- 音:40dBA前後
生活リズムを整える
眠りにつきやすくなる習慣のひとつに、生活リズムを整えることが挙げられます。生活リズムを整えることで、体内時計のリズムを正常に保ちやすくなると言われています。
体内時計が整っていると、特定の時間が近づくにつれて自然と眠気が生じやすくなり、スムーズに入眠できるようになるでしょう。
不眠による心身への影響
不眠は、心身にさまざまな悪影響を及ぼす可能性が高いです。
不眠が続くと疲労が回復せず、日中に眠気が残ってしまうことも少なくありません。その結果、注意力が散漫になったり、集中力が低下して作業効率が落ちたりする傾向があります。
不眠による心身への影響としては、以下のような点が挙げられます。
- 生活習慣病のリスクが上昇する
- 免疫力が下がる
- モチベーションが下がる
- 集中力が下がる
- 不安になりやすくなる
上記のような症状がある場合は、今回ご紹介した対処法を試してみると良いでしょう。
眠れない時に関連するよくある質問
眠れない時の対処法を試しても眠れない場合はどうすれば良いですか?
眠れないときに対処法を試しても効果がない場合は、一度起きて寝具から離れることが有効な方法のひとつと言えます。
眠れない状態が続くと気分が沈み、さらに入眠しにくくなることがあります。また、眠れない経験が重なることで、寝室を「眠れない場所」として認識してしまう可能性もあります。
そのようなときは、一度起きて本を読んだり、軽いストレッチをしたりして、自然な眠気を促すのが効果的です。
不眠症にはどのようなタイプがありますか?
不眠症には、主に4つのタイプがあると言われています。具体的には、以下のような種類があります。
- 入眠障害:横になっても目が冴えて、寝つけない
- 熟眠障害:睡眠時間は足りているのに、朝の目覚めがすっきりしない
- 中途覚醒:一度眠っても、夜中に何度も目が覚めてしまう
- 早朝覚醒:朝方に早く目が覚めてしまい、その後なかなか寝つけない
一時的な不眠は「短期不眠」に分類され、数日から数週間で自然に回復することが多いです。しかし、不眠の状態が1カ月以上続き、日常生活に支障をきたしている場合は、「慢性不眠症」である可能性が高いと考えられます。
眠れるツボはありますか?
いくつかのツボには、刺激することで眠りやすくなる効果が期待できるものがあります。代表的な「眠れるツボ」は、以下の通りです。
- 百会:頭頂中央の、指を当てるとわずかにへこむ感覚のある部分
- 合谷:手の甲側で、親指と人差し指の骨が交わるあたりの部分
- 安眠:耳の裏側の骨の出っ張りを起点に、指1本下がった部分
- 内関:手首から指2本分下がった位置にあるツボで、押すとピリッとした刺激を感じる部分
- 失眠:足の裏にある、かかとの中心あたりのくぼんだ部分
眠気を促すツボを刺激することで、心身のこわばりがほぐれ、副交感神経が優位になるため、眠りやすくなるとされています。
眠れない時に横になるだけで効果はありますか?
眠れないときでも横になることで、リラックス効果や身体を休める効果が期待できます。横になってリラックスできると、脳の活動が抑えられ、入眠しやすくなることも少なくありません。また、身体が休まることで、疲労回復にもつながる場合があります。
【監修者プロフィール】

江東こころのクリニック院長
谷本 幸多朗医師
九州大学医学部卒業後、帯広第一病院にて救急医療や外科及び内科の研修を経験する。
2013年より久喜すずのき病院にて精神科急性期医療を後期研修し精神保健指定医となる。
2018年より江東区にて一般メンタルクリニックに加えて認知症デイケアを併設した物忘れ外来も行う精神科クリニックである江東こころのクリニックを開業し、現在に至る。
▼主な経験
・精神保健指定医の経験あり
・製薬会社主催の各講演会や地域の医療職対象の勉強会において講演や座長の経験多数あり