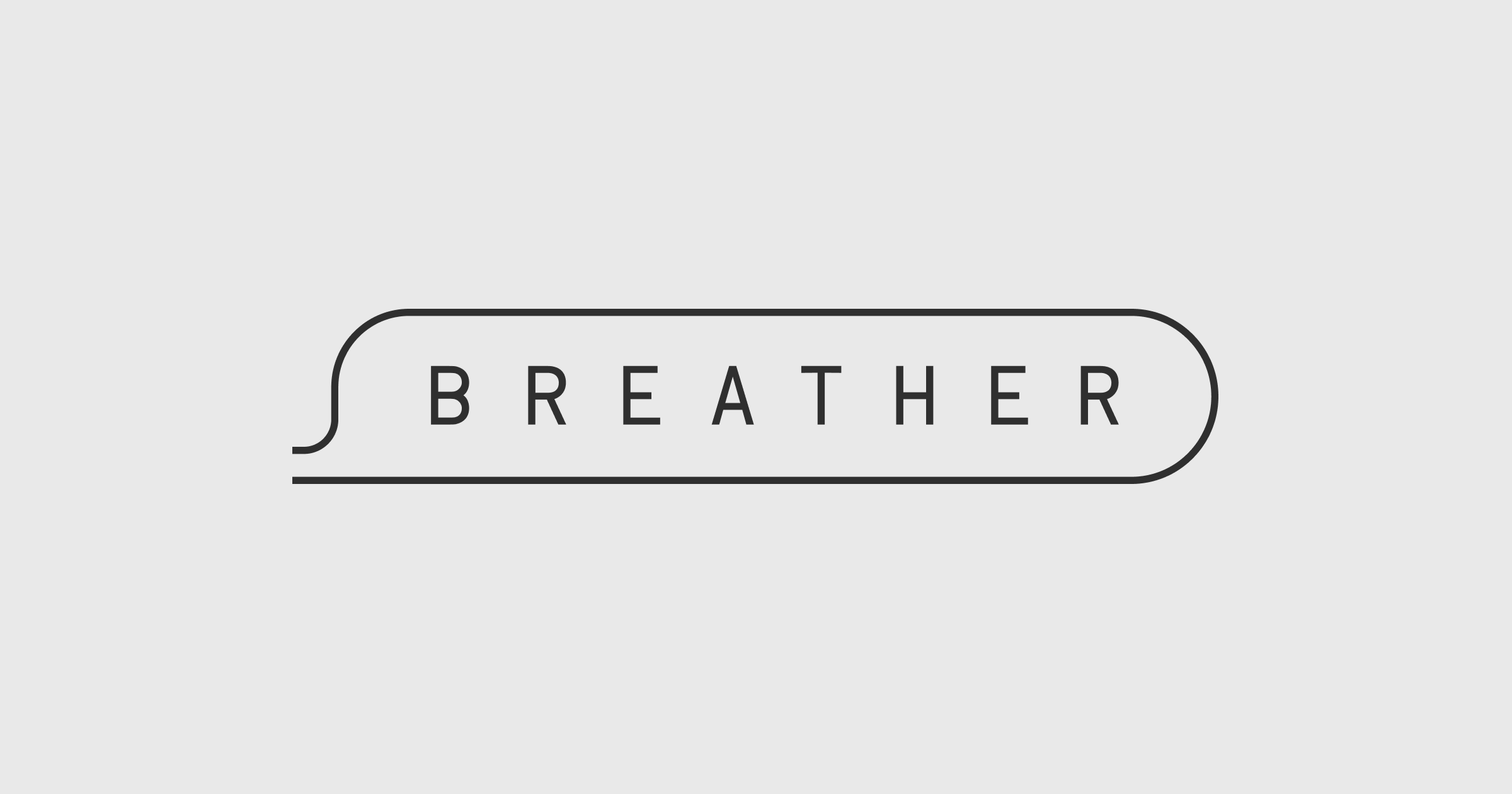目次
眠いのに寝れない時にできる対処法
眠いのに寝れない時には、以下のような対処法があると言えます。
- 深呼吸をする
- 好きな音楽を楽しむ
- ストレッチをする
- 好きな香りをかぐ
- ツボを押す
- 寝ようと焦らない
- ナイトルーティンを行う
深呼吸をする
眠いのに寝れない時にできる対処法のひとつとして、深呼吸をすることが挙げられます。
就寝時に浅い呼吸をしていると、自律神経が乱れて交感神経が高まってしまい、心や身体が緊張してリラックスできていない状態になりやすいです。そのため、眠いのに寝れなくなってしまう場合があります。
こうしたときに深呼吸を行うことで、自律神経のバランスが整い、副交感神経が優位になることで リラックス効果が得られ、眠りにつきやすくなるとされています。
なお、深呼吸をする際は、胸で呼吸をする「胸式呼吸」ではなく、お腹を膨らませるように呼吸する「腹式呼吸」を意識すると、より高いリラックス効果が期待できます。
深呼吸習慣化デバイス「ston s」

- 「ston s」は、エナジードリンクでも、電子タバコでもない深呼吸を習慣化することを目的としたデバイス
- 罪悪感0で瞬間リフレッシュが可能
- 充電の必要がなく、どこでも持ち運びできる
好きな音楽を楽しむ
好きな音楽を楽しむことも、眠いのに寝れない時にできる対処法と言えます。
好きな音楽を聞くと副交感神経が優位になり、血圧や心拍数が安定して、リラックスできると言われています。
快適と感じる音楽に浸ることで、リラックスしている時に出ると言われているα(アルファ)波という脳波が増加する可能性が高いです。
そのため、寝る前などに快適と感じる自分の好きな音楽を楽しむと、眠いのに寝れないという症状を解消できる見込みがあります。
例えば次のような音楽が、リラックス効果が高いと考えられています。
- 歌詞の入っていないインストゥルメンタル
- 小鳥のさえずりや波の音などの自然音が入った音楽
- クラシック音楽
自分が好きな音楽であってもアップテンポな曲や歌詞の入った曲は、脳が刺激されて覚醒してしまう場合があるため、眠いのに寝れない時に聞くのは避けた方が良いと言えるでしょう。
ストレッチをする
眠いのに寝れない時にできる対処法には、ストレッチをするということも考えられます。
ストレッチは、関節や筋肉をほぐして血のめぐりを良くし、心拍数や血圧を下げる効果があると言われています。
また、ストレッチは自律神経を整え、副交感神経を優位にして、リラックス効果をもたらす可能性が高いです。そのため、眠いのに寝れない時にストレッチを行うと安眠に繋がる場合があります。
ただし、勢いをつけてストレッチしたり、やりすぎたりすると、逆に交感神経を活発にしてしまい、寝つきが悪くなってしまうケースがあるため、注意が必要と言えます。
好きな香りをかぐ
眠いのに寝れない時にできる対処法として、好きな香りをかぐこともあると言われています。
人が香りを嗅いだ際には、直接的に脳へ刺激が伝わると考えられています。
嗅覚は、他の五感と比べて感情や自律神経をつかさどる大脳辺縁系へと情報が伝達されるスピードが早い可能性が高いです。そのため、好きな香りをかぐと活発な状態から休息の状態へ、神経をシフトチェンジさせやすいです。
ツボを押す
眠いのに寝れない時にできる対処法には、ツボを押すという方法もあります。
身体の色々な箇所にあるツボの考え方は東洋医学に基づいていると言われています。ツボを刺激することでリラックス効果が得られる可能性が高いため、眠いのに寝れない時に対処法となる見込みがあります。
例えば、足のかかとの真ん中のややくぼんだところにある失眠は、寝れない時に刺激すると副交感神経が優位になって眠れるようになる場合が多いです。失眠は押して刺激するのみではなく、お灸や湯たんぽなどで温めても効果が見込めます。
また、頭の頂点にある百会を刺激すると、自律神経が整い、眠りやすくなる可能性が高いです。
その他にも、手を軽く握った際の人差し指と中指の指先の真ん中にある労宮も、心を落ち着かせてリラックスさせるツボと考えられています。
寝ようと焦らない
寝ようと焦らないことも、眠いのに寝れない時にできる対処法と言えるでしょう。
翌日のことを考えて、早く寝なくてはならないと慌てる気持ちが精神的なストレスとなり、眠いのに寝れなくなる場合が多いです。
寝れないと焦りながらベッドにいると、ベッドそのものが寝れない場所だと脳にインプットされてしまうと言われています。
このような時は一度ベッドから起き上がって、アロマを楽しんだり、軽いストレッチをするなど、リラックスできることをすると良いでしょう。
寝ようと焦らずに、一旦自分がリラックスできる別のことに注意を向けることで、気持ちが穏やかになり、改めてベッドに入った時に寝れるようになる可能性が高いです。
ただし、ベッドから出てすることとしては、自分がリラックスできると思っていることでも、激しい運動やスマートフォンなど脳を興奮させるものは避けるべきと言えます。
ナイトルーティンを行う
ナイトルーティンを行うことは、眠いのに寝れない時の対処法となる可能性があります。
ナイトルーティンとは毎晩決まった動作や行動を繰り返し行うことを指すと言えます。毎晩寝る前に同じ行動をすることで、脳が寝る時間だと認識するようになり、スムーズに寝れるようになると考えられています。
また、心身をリラックスさせるようなナイトルーティンを行うとストレスが緩和され、脳や身体を休ませるスイッチが入り、質の高い睡眠に繋がる可能性が高いです。
ナイトルーティンの具体的な例として、例えば軽い読書やリラックスできる音楽を聴くことなどが挙げられるでしょう。
無理なナイトルーティンの計画を立てても、それが実践できないことがストレスになってしまうと逆効果になるため、注意が必要と言えます。
眠いのに寝れない主な原因
眠いのに寝れない主な原因として、以下が挙げられます。
- ストレスの蓄積
- 就寝直前の運動
- ホルモンバランスの乱れ
- 睡眠環境の悪さ
- 生活習慣の乱れ
- 運動不足
- 過度な飲酒
- 就寝前の電子機器の使用
- 加齢
- 過覚醒
- 不眠に繋がる病気
ストレスの蓄積
眠いのに寝れない主な原因のひとつに、ストレスの蓄積が挙げられます。
ストレスが蓄積されると自律神経が乱れ、交感神経が優位になる可能性が高いです。これにより、交感神経が優位になると脳が覚醒し、眠いのに寝れなくなることがあると言われています。
就寝直前の運動
就寝直前の運動が、眠いのに寝れない原因となっている可能性があります。
運動をすると心拍数が増え、アドレナリンが分泌されると言われています。そのため、就寝直前に運動をすると神経が高ぶった状態となって、眠いのに寝れない場合が多いです。
また、運動をすることで体温が上がるということも、眠気が抑えられてしまって寝れない原因となる見込みがあります。
ホルモンバランスの乱れ
眠いのに寝れないのは、ホルモンバランスの乱れが原因であるケースがあります。
人間は深部体温が下がると、眠気を感じるようになると言われています。
女性は、排卵から月経までプロゲステロンという女性ホルモンの一種が増える可能性が高いです。プロゲステロンが増えてホルモンバランスが乱れると、通常時よりも体温が上がると考えられています。
つまり、排卵から月経までは深部体温も下がりにくく高い状態のため、スムーズな眠りに繋がるような自然な眠気を感じにくくなる可能性があります。
また、その他の女性ホルモンのひとつであるエストロゲンは排卵後から減少すると言われています。このエストロゲンは精神状態を安定させてストレスを軽減させる働きが見込めます。
そのため、エストロゲンが減少するとストレスを感じやすく、眠いと感じているにもかかわらず寝れなくなる可能性が高いと言えるでしょう。
睡眠環境の悪さ
眠いのに寝れない場合の主な原因として、睡眠環境の悪さが考えられます。
睡眠環境は、脳や心身をリラックス状態にするために大切である場合が多いです。
例えばマットレスや枕などが身体に合っていない場合も、リラックスできずに眠いのに寝れなくなるケースがあります。
また、明るすぎる照明の光を浴びると、メラトニンの分泌が抑制されて寝れなくなると言われています。
その他にも寝室の温度も高すぎたり低すぎたりすると深部体温が下がらず、眠気を感じにくい可能性が高いです。
生活習慣の乱れ
生活習慣の乱れによって、眠いのに寝れない場合が多いです。
人間の身体には約25時間周期の体内時計が備わっていると考えられています。体内時計がリセットされてからおよそ14~16時間程度で、メラトニンが分泌されて身体を休めるモードになり、眠りへと誘われると言われています。
そのため、生活習慣が乱れて体内時計が狂ってしまうと、眠いはずなのにすんなり眠れない状態になる可能性が高いです。
例えば、平日に寝れなかった分を休日に取り戻そうと、休みの日にお昼近くまで寝てしまったりした場合もリズムが崩れて体内時計が狂ってしまうと言えます。
また、夜更かしして遅くまで照明の明るい光を浴び続けることでも生活習慣の乱れに繋がる場合が多いです。
運動不足
運動不足も眠いのに寝れない主な原因のひとつと言えます。
運動が不足すると自律神経のバランスが崩れ、眠いのにもかかわらず寝れないといった症状に陥る可能性が高いです。
また、昼間の活動量が少ない場合、脳が昼と夜のメリハリを感じにくくなり、体内時計が乱れることで自然な眠気を感じにくくなることもあります。
ただし、寝る直前や激しすぎる運動はストレスホルモンが分泌されて脳が覚醒し、逆に寝れなくなる場合があるため、注意が必要です。
過度な飲酒
眠いのに寝れないのは、過度な飲酒が原因となっていることがあります。
飲酒によってアルコールを摂取すると、脳の中枢神経が抑えられて眠くなる可能性が高いです。
ただしこの効果は一時的なもので、摂取してから2~3時間後にはアルコールが体内で分解され、アセトアルデヒドが発生すると考えられています。
アセトアルデヒドは覚醒作用を備えており、夜中に目が覚めてしまったり、眠いのに寝れなくなってしまうことを引き起こす場合が多いです。
就寝前の電子機器の使用
眠いのに寝れないのは、就寝前の電子機器の使用が原因となっている場合があります。
電子機器の画面から発生するブルーライトを浴びると、眠りへと誘うメラトニンというホルモンの分泌が抑えられてしまい、スムーズに寝れないといった状態になる可能性が高いです。
また、寝る前に電子機器の強い光を浴びることで体内時計が乱れてしまい、眠りの妨げとなることも考えられます。
例えば、ベッドに横になりながらスマートフォンやタブレットを使用したり、寝る直前までパソコンを使っていたりすると、画面から発せられるブルーライトの影響を受ける場合が多いです。
加齢
加齢も、眠いのに寝れない主な原因のひとつと言えるでしょう。
加齢によって睡眠へと導くホルモンであるメラトニンの分泌が減り、寝れなくなると考えられています。
また、高齢になって仕事を引退するなどして生活リズムが乱れやすくなることも、眠いのに寝れなくなる原因となる可能性が高いです。
それに加えて、高齢になると活動量が減って眠くなりにくいというケースもあります。
過覚醒
眠いのに寝れない主な原因として、過覚醒もそのひとつと言われています。
過覚醒とはストレスなどから交感神経が優位となり、常に興奮した状態になることと言えます。
過覚醒による脳の興奮でリラックスモードになりにくくなるため、身体は疲れていて眠くても寝れないということが起きる可能性が高いです。
不眠に繋がる病気
不眠に繋がる病気が原因となって、眠いのに寝れない状態になっていることが考えられます。
精神疾患によって眠いのに寝れない可能性があります。例えば、うつ病や自律神経失調症も不眠に繋がると言われています。
また、痛みやかゆみの症状が出る内科的な疾患によって、眠さは感じているのにうまく寝れない状態になる場合も多いです。
眠いのに寝れない時に考えられる病気
眠いのに寝れない時には、以下のような病気である可能性があると考えられます。
- 適応障害
- 自律神経失調症
- 睡眠障害
- 双極性障害
- うつ病
適応障害
眠いのに寝れない時に考えられる病気のひとつとして、適応障害が挙げられます。
適応障害とは、原因がストレスによって引き起こされる症状のことと言えます。この適応障害の症状によって、生活に支障が出る場合が多いです。
また、適応障害を引き起こすほどのストレスを感じると、それによって交感神経が優位となり、眠いと感じていたとしても寝れなくなる可能性があります。
自律神経失調症
眠いのに寝れない時には、自律神経失調症である可能性があります。
自律神経失調症とは、ストレスによって自律神経がうまくコントロールできなくなり、内臓機能に様々な影響を及ぼす病気と言われています。
自律神経失調症により、夜寝る時にも交感神経が優位になってしまい、眠いと感じていても寝れなくなる場合が多いと言えるでしょう。
睡眠障害
眠いのに寝れない時に考えられる病気には、睡眠障害があると言われています。
睡眠障害とは、睡眠に何らかの支障を抱えている状態のことを言う場合が多いです。睡眠障害の症状には不眠症も挙げられ、ストレスによって寝付けないケースも考えられます。
双極性障害
双極性障害も、眠いのに寝れない時に考えられる病気のひとつと言われています。
双極性障害とは躁うつ病とも言われ、テンションが極端に高い躁の状態と、極度に気分が落ち込むうつの状態が繰り返される病気と言えます。
例えば、躁の状態ではテンションが上がって活動意欲も高いため、寝付くまでに多くの時間を要する場合が多いでしょう。
うつ病
眠いのに寝れない時には、うつ病である可能性も考えられます。
うつ病とは、脳機能がうまく働かず、やる気が起きなかったり、気持ちが落ち込んでしまったりする疾患と言われています。
うつ病を患っていると、精神状態が不安定になるため、寝る時に気になることを考えすぎてしまったり、過度に不安を感じてしまったりして寝れなくなる可能性が高いです。
また、眠れない状態が続くとうつ病の症状が悪化し、溜まったストレスでより眠れなくなるという悪循環に陥ってしまうこともあると考えられています。
眠いときに寝るために日常的にできること
眠いときに寝るためには、日常的に以下のようなことを行うと良いでしょう。
- 適度な運動を習慣化する
- 就寝直前に電子機器を使用しない
- 就寝直前に食事をとらない
- 入浴をする
- 生活習慣を整える
- 起床後に日光を浴びる
- 栄養バランスを意識して食事をする
- 睡眠環境を整える
- 過度な飲酒を避ける
適度な運動を習慣化する
眠いときに寝るために日常的にできることのひとつとして、適度な運動を習慣化することが挙げられます。
日中に適度な運動をして自律神経の交感神経を優位にしておくと、夜に自然と副交感神経が優位となりリラックスモードになると言われています。
この適度な運動を習慣化すると、体内時計のリズムが整い、睡眠に良い効果をもたらす見込みがあります。
また運動によって上がった体温が、下がり始めた時に眠くなりやすいです。
例えば、軽いジョギングやウォーキングなどの有酸素運動が適していると言えます。
ただし寝る直前の運動や激しすぎる運動は、交感神経を優位にして脳が興奮状態になってしまうケースがあるため注意が必要と言えるでしょう。
就寝直前に電子機器を使用しない
就寝直前に電子機器を使用しないことは、眠いときに寝るために日常的にできることと言われています。
電子機器のディスプレイから発生するブルーライトを浴びると、眠気を誘うホルモンであるメラトニンの分泌が減る可能性が高いです。
また、就寝直前に電子機器の強い光を浴びることで体内時計が乱れてしまい、眠りの妨げとなることも考えられます。
そのため、眠いときに寝るためには就寝直前に電子機器を使用しない方が良いと言えます。
例えば眠いときに寝るためには、ベッドに横になりながらスマートフォンやタブレットを使用しない方が良い場合が多いです。
また、寝ながらスマホを操作する以外にも画面から発せられるブルーライトの影響を受ける可能性があります。そのため、寝室以外でも就寝直前までパソコンを操作しないことも、眠いときに寝るために日常的にできることと考えられています。
就寝直前に食事をとらない
眠いときに寝るために日常的にできることとして、就寝直前に食事をとらないことが挙げられるでしょう。
就寝直前に食事をとると、血糖値が上がって脳が覚醒し、寝付きにくくなる可能性が高いです。
また眠りにつこうとしている間も、消化のために胃腸の活動が活発になり、身体が休息モードにならないと考えられています。
そのため、寝る2〜3時間前には食事を終えておくことを目標とするのが良い場合が多いです。
中でも辛みの強いものや油分の多いものは消化しにくく、身体への負担も大きいため、眠りに落ちにくくなると言われています。
脂っぽい揚げ物や脂肪分が多い肉などは、消化に時間がかかるため、就寝直前に食べることは避けるべきと言えます。
入浴をする
入浴をすることも、眠いときに寝るために日常的にできることと考えられています。
ぬるめのお湯にゆっくりと浸かることで、副交感神経が優位となり、リラックスしやすいです。
また入浴をすることで体温が上がり、この上がった体温が下がる時に眠気を感じると言われています。
具体的には眠ろうとしている時間の1~2時間ほど前までに、38~40度程度のお湯に20分ほど時間をかけてゆっくり入浴すると良い場合が多いです。
お湯の温度が熱すぎる場合や、長時間の入浴は逆に身体に負担がかかり、脳が覚醒してしまう可能性があるため注意が必要と言えます。
生活習慣を整える
眠いときに寝るために日常的にできることには、生活習慣を整えることがあると言われています。
人間の身体には体内時計が備わっており、その周期はおよそ25時間と考えられています。この体内時計がリセットされてからおよそ14~16時間経つと、眠りへと誘うホルモンであるメラトニンが分泌される可能性が高いです。
このリズムに合わせて生活習慣を整えると、夜になったら自然と眠気を覚えるようになり、眠いときに寝られるようになる見込みがあります。
起床後に日光を浴びる
起床時に日光を浴びることは、眠いときに寝るために日常的にできることのひとつと言えます。
起床時に日光を浴びると、体内時計がリセットされると言われています。日光を浴びることで、眠くなるホルモンであるメラトニンの分泌が抑制されて目覚めやすいです。
また、ここから14~16時間後に眠気を感じるようになると考えられているため、夜になると自然と寝れるようになることが見込めます。
栄養バランスを意識して食事をする
眠いときに寝るために日常的にできることのひとつとして、栄養バランスを意識して食事をすることが挙げられます。
疲労が軽減されたり、睡眠の質が向上すると言われている栄養を意識的に摂取することで、眠いときに寝られるようになる可能性が高いです。
例えばたんぱく質に含まれるアミノ酸のひとつであるトリプトファンは、セロトニンや睡眠を促すホルモンであるメラトニンの原料となると考えられています。
トリプトファンはバナナや大豆製品に多く含まれると言われています。トリプトファンを多く含む食材を朝食に取ることで、体内で時間をかけてメラトニンへと変化していき、夜の眠いときに寝られるようになる場合が多いです。
睡眠環境を整える
睡眠環境を整えることは、眠いときに寝るために日常的にできることであると言われています。
音がうるさかったり、光がまぶしかったりすると脳が刺激されて興奮状態となり、眠いのに寝られなくなる場合が多いです。
睡眠環境は、脳や心身をリラックス状態にするために快適に整えることが重要な要素であると考えられています。
例えば締め付けられるような服装で寝ようとすると、リラックスできずに眠いのに寝れなくなるケースがあるため、ゆったりとした身体に合った服装が良いと言えます。
また、寝室の温度も高すぎたり低すぎたりしないように調整することで深部体温を下げて眠気を誘発できる可能性が高いです。
過度な飲酒を避ける
眠いときに寝るために日常的にできることのひとつに、過度な飲酒を避けることがあると言えます。
飲酒をしてから2~3時間後には体内でアルコールが分解されて、アセトアルデヒドが発生すると考えられています。
アセトアルデヒドは覚醒作用があるため、夜中に目が覚めてしまったり、眠いのに寝れなくなってしまう状態を引き起こす可能性が高いです。
また、アルコールには利尿作用があるため、寝ている間にトイレに行きたくなって夜中に目が覚め、寝れなくなってしまうというケースもあります。
寝れないことによる心身の影響
寝れないことで、次のような影響が心身に及ぶ可能性があります。
- 疲労が蓄積される
- 情緒が不安定になる
- 集中力や判断力が低下しやすくなる
- 免疫力が低下しやすくなる
疲労が蓄積される
寝れないことによる心身の影響のひとつとして、疲労が蓄積されることが挙げられます。
日中に溜まった疲労は睡眠によって解消されると言われています。また、ノンレム睡眠の間は筋肉など身体のみではなく、脳も休息モードになると考えられています。
そのため、寝れないと疲労が回復せずに、次の日に持ち越されてしまいどんどん溜まっていってしまう可能性が高いと言えます。
情緒が不安定になる
寝れないことによる心身の影響には、情緒が不安定になるということもあると言えます。
寝ている間に辛いという感情や苛立ちなどのマイナスの感情が整理されてストレスが軽減されると考えられています。
そのため、寝れないことで気持ちがマイナス思考になり、抑うつや不安などで情緒が不安定になる可能性が高いと言えます。
集中力や判断力が低下しやすくなる
集中力や判断力が低下しやすくなることは、寝れないことによる心身の影響のひとつと言えるでしょう。
寝れない状態が継続すると、脳の前頭葉に悪影響を及ぼすとされており、脳内の老廃物が排出されにくくなって神経細胞の働きが鈍くなると考えられています。
その結果、認知機能が衰え、集中力や判断力が低下しやすくなる場合が多いと言えるでしょう。
免疫力が低下しやすくなる
寝れないことによる心身の影響として、免疫力が低下しやすくなるということが挙げられます。
寝ている間に成長ホルモンが分泌され、細胞の傷みを改善したり、免疫物質を作り出したりしていると言われています。
また、睡眠をとることによって自律神経のバランスが整い、免疫機能の働きが滞りなく行われるようになると考えられています。
このため寝れない状態が続くと、免疫細胞が減少してうまく機能しなくなり、免疫力が低下しやすくなる可能性が高いと言えます。
眠いのに寝れないことに関連するよくある質問
眠いのに寝れない時に目をつぶっているだけでも意味はありますか?
眠いのに寝れない時に目をつぶっているのみでは、あまり意味がないと言われています。
例えば、ベッドなどで眠いのに寝れないというストレスを抱えながら目をつぶっていると、脳がそこは眠れない場所だと認識してしまうケースがあります。
また、眠いのに寝れない時にただ目をつぶっている場合、気になっていることや不安なことなどを無駄に考えすぎてしまう可能性が高いです。
ただし、目をつぶって目からの情報が遮断されることで、脳の機能が休まることが期待できると言えます。
寝れなくなる人にはどのような特徴がありますか?
寝れなくなる人には、以下のような特徴があると言えます。
・環境的な特徴
- 家族にも寝れなくなる人がいる
- 周囲の音がうるさいなど、寝にくい環境に置かれている
- 日々ストレスや不安を抱えている
・性格的な特徴
- 不安症
- 責任感が強い
- 心配性
- 完璧でないと気が済まない
家族にも同じように寝れなくなる人がいる場合、遺伝の可能性が考えられます。
また、騒音が激しい場所で寝ざるを得ない、夜勤などで明るい時間に寝なくてはならないなど寝にくい環境に置かれている場合、寝れなくなることが多いです。
さらに、日ごろからストレスを強く感じていたり、心配や不安を抱えていると、リラックスすることができず、寝れなくなるケースが見られます。
寝れない時に横になるのみでも意味はありますか?
寝れない時には横になるのみでも意味があると言われるのは誤解で、より眠れなくなる可能性が高いと言えます。
寝れない時にただ横になっていると、寝れないことに意識が集中してしまい、よりストレスを感じて寝れなくなる場合があります。
また、寝れないことが気になりながら寝室で横になっていると、寝室自体に入ることがストレスになって恐怖を感じる場合があるため、注意が必要です。
【監修者プロフィール】

江東こころのクリニック院長
谷本 幸多朗医師
九州大学医学部卒業後、帯広第一病院にて救急医療や外科及び内科の研修を経験する。
2013年より久喜すずのき病院にて精神科急性期医療を後期研修し精神保健指定医となる。
2018年より江東区にて一般メンタルクリニックに加えて認知症デイケアを併設した物忘れ外来も行う精神科クリニックである江東こころのクリニックを開業し、現在に至る。
▼主な経験
・精神保健指定医の経験あり
・製薬会社主催の各講演会や地域の医療職対象の勉強会において講演や座長の経験多数あり