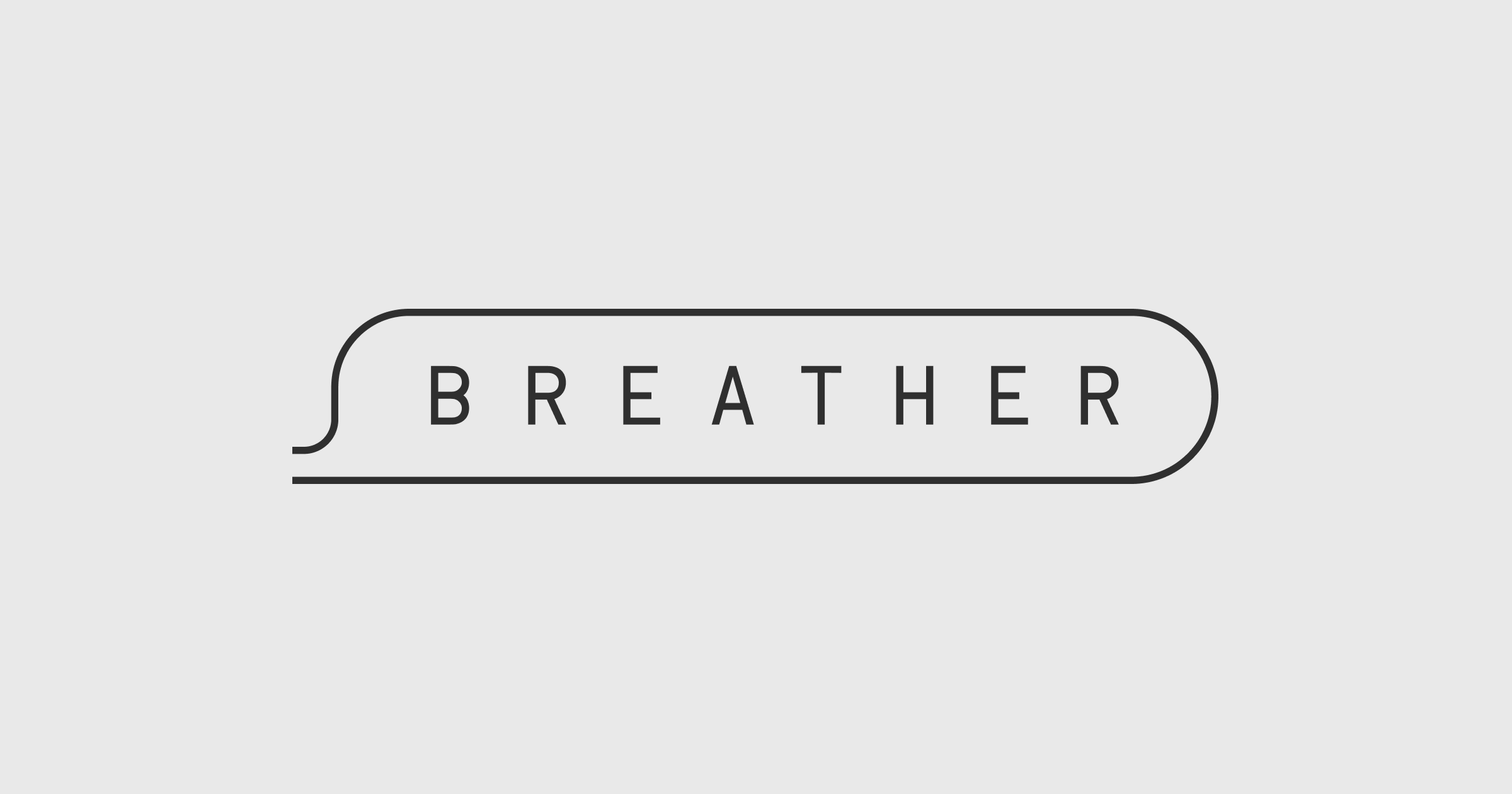目次
寝不足とは
寝不足とは一般的に、その人にとって適切な時間の睡眠をとれていない状態を指す場合が多いです。
個人によって差はあるものの、成人の1日に必要な睡眠時間は6~8時間程度と言われています。睡眠時間が短いと、睡眠が足りていない状態になり、寝不足になりやすいです。
さらに、寝不足であるかどうかの判断基準には、睡眠自体の質や深さも重視される傾向にあります。睡眠時間が足りていても、睡眠の質や深さが不足していると寝不足の状態に陥る可能性もあるため、注意が必要です。
寝不足になる原因
質の良い睡眠に繋がるいくつかの条件を満たせていないことが、寝不足の状態に陥る原因のひとつと考えられています。
寝不足になる代表的な原因は、以下の通りです。
- 睡眠時間が足りていない
- 睡眠の質が悪い
- 規則正しい睡眠ができていない
睡眠時間が足りていない
寝不足になる原因のひとつとして、睡眠時間が足りていないことが挙げられます。睡眠時間の長さは、適切に睡眠が取れているのかを確認する要素として重視される場合が多いです。
必要な睡眠時間は個人によって異なるものの、一般的には成人において6~8時間程度が目安と言われています。
睡眠時間が短い場合や、休めたと感じられていない状態では、質の良い睡眠ではないと判断されやすいでしょう。
睡眠の質が悪い
睡眠の質が悪いことも、寝不足に繋がる原因のひとつです。
適切な睡眠時間を確保している場合でも、休めたという感覚が得られない場合もあります。これは、睡眠の質が悪く眠りが浅いことが原因と言われています。
以下は、睡眠の質が悪くなる要因の一例です。
- 寝付きが良くない
- 睡眠中に呼吸が止まっている
- ストレスを抱えている
- ブルーライトを浴びすぎている
- 不規則な生活習慣をしている
- 身体に痒みや痛みなどの不快感が生じている
また、何かしらの病気を発症しており、睡眠の質が下がっている可能性もあるため、注意が必要です。睡眠の質を悪化させる代表的な病気は、以下の通りです。
- 概日リズム睡眠・覚醒障害
- 睡眠時無呼吸症候群
- 周期性四肢運動障害
- むずむず脚症候群
規則正しい睡眠ができていない
規則正しい睡眠ができていないと、寝不足になりやすい傾向にあります。
睡眠のリズムが崩れてしまうと、体内時計が乱れやすくなるでしょう。
体内時計が適切に機能していないと、身体の活動状態と休息状態の切り替えが難しくなりがちです。その結果、睡眠時間が安定しなくなり、睡眠の質が下がってしまうことが少なくありません。
寝不足が続くことによる悪影響・症状
寝不足が続くことによる悪影響として、以下のような内容が挙げられます。
- ストレスを感じやすくなる
- 体の疲れがとれにくくなる
- 集中力や判断力が低下する
- めまいや頭痛を起こしやすくなる
- 病気になりやすくなる
ストレスを感じやすくなる
ストレスを感じやすくなることは、寝不足が続いている人に多く見られる特徴のひとつです。
適切な睡眠が取れていないと、精神的な負担や疲れが解消されないことが多いです。そのため、寝不足の状態ではトラブルやネガティブな感情に対する耐性が低下し、ストレスを感じやすくなります。
また、ストレスを抱えていると心身の緊張が続きやすくなり、眠りが浅くなる傾向にあります。その結果、さらに寝不足になるという負の連鎖に陥りかねません。
体の疲れがとれにくくなる
寝不足による悪影響のひとつとして挙げられるのが、体の疲れがとれにくくなることです。睡眠は、肉体のメンテナンスにおいて重要な役割を果たすと考えられています。
具体的には、睡眠中に分泌される成長ホルモンが、疲労やストレスを軽減する働きを持つとされています。寝不足になると、このような心身の回復や調整の働きが不十分な状態になりがちです。
集中力や判断力が低下する
寝不足が続くと、集中力や判断力が低下する傾向にあります。睡眠により、脳も休まることで、集中力と判断力を高めることができると考えられています。
しかし、寝不足の状態では、満足に脳を休ませることができず、情報の理解や思考の整理がスムーズに行えなくなり、集中力や判断力の維持が難しくなりがちです。
例えば、寝不足によって脳が本来の機能を発揮できず、業務中に失敗する場面が増えてしまうという人も少なくありません。
めまいや頭痛を起こしやすくなる
寝不足になると、めまいや頭痛といった症状がしばしば見られます。寝不足の状態では、身体のさまざまな調整機能が適切に働かなくなる場合が多いです。
寝不足により発生する頭痛は、自律神経のバランスが崩れることが原因のひとつとされています。これは、交感神経の働きが強い状態が続いて血管が縮まったままになり、血の流れが滞ってしまうと考えられているためです。
さらに、自律神経が不安定な状態になると、心拍数や血圧が変動しやすくなる傾向にあります。心拍数や血圧の変動は、脳への血流の巡りが悪くなることに繋がり、めまいを引き起こす要因となる場合があります。
なお、めまいには体の平衡感覚を調整するとされている耳の三半規管が関係している可能性も高いです。この三半規管が寝不足の影響で乱れ、めまいを引き起こすケースもあります。
病気になりやすくなる
寝不足になると免疫力が低下し、病気にかかるリスクが高くなりやすいです。睡眠は、成長ホルモンやメラトニンなどのホルモンの分泌と密接に関わっているとされています。
これらのホルモンは、免疫機能のメンテナンスや向上に役立つと考えられており、健康維持に一定の役割を果たしていると見られています。
しかし、寝不足の状態では免疫機能を正常に維持することが難しく、体調を崩してしまう可能性が高いです。そのため、寝不足の人は、かぜの症状などが見られるケースが少なくありません。
加えて、寝不足により以下のような病気に繋がる恐れがあると考えられています。
- 肥満症
- 糖尿病
- 高血圧
- うつ病
- 認知症 など
寝不足をすぐに解消する方法
寝不足をすぐに解消できる可能性のある方法は、以下の通りです。
- 深呼吸をする
- 仮眠をとる
- ブドウ糖を食べる
- ツボ押しを行う
- 体をつねる
- シャワーを浴びる
- 冷たい水で体を冷やす
- 体を動かす
- ストレッチをする
- 明るい方へ目を向ける
- メンソールを首や鼻につける
- ガムをかむ
深呼吸をする
寝不足をすぐに解消する方法のひとつに、深呼吸をすることが挙げられます。
深呼吸を行うと、酸素を体内に取り込みやすいです。この深呼吸により脳に酸素を送ることで、頭が冴えて一時的な眠気の軽減が期待できると言えるでしょう。
深呼吸習慣化デバイス「ston s」

- 「ston s」は、エナジードリンクでも、電子タバコでもない深呼吸を習慣化することを目的としたデバイス
- 罪悪感0で瞬間リフレッシュが可能
- 充電の必要がなく、どこでも持ち運びできる
仮眠をとる
仮眠を取ることは、寝不足を解消するのに有効な手段になる場合があります。これは、仮眠を取ることで脳が休まり、眠気をやわらげる効果が期待できるためです。さらに、実際に眠らなくても、目を閉じて静かに休むことで一定の効果があるとされています。
なお、仮眠の時間は5~15分程度に抑えることが重要と言えるでしょう。これは、15分を超えて眠ってしまうと、深い睡眠に入りやすくなる傾向があるためです。
また、昼間に長時間熟睡してしまうと、目覚めが悪くなったり、かえって強い眠気を感じたりする可能性があるため注意が必要と言えます。
ブドウ糖を食べる
ブドウ糖を食べることは、寝不足の解消方法として役立つ場合があります。人間は、脳にエネルギーが足りない状態だと、眠気を感じることが少なくありません。
ブドウ糖は、脳の活動を支える主要な栄養源のひとつとされています。また、ブドウ糖の摂取は、低血糖状態による眠気の誘発を防ぐ効果も期待できます。
しかし、ブドウ糖を大量に摂取すると、血糖値が短時間で過剰に上昇してしまうことが多いです。その結果、インスリンが必要以上に分泌されて血糖値が下がりすぎ、かえって眠気を感じやすくなる可能性があります。
ツボ押しを行う
一部のツボは、眠気を覚まして寝不足を解消する効果が期待できます。
ツボとは、身体に点在する神経や経絡が交差・集中すると言われている部分です。ツボのなかには、眠気覚ましに役立つと考えられているものもあります。
眠気覚ましの効果が期待できるツボとして、以下のものが挙げられます。
- 天柱:後頭部の生え際付近にある、首の骨の両側のへこみ
- 合谷:手の甲の親指と人差し指の付け根が合わさる部分から、少し人差し指側の位置
- 太衝:足の親指と人差し指の骨の付け根近くにあるへこみ
- 中衝:手の中指の爪の生え際、親指側の端付近
- 神門:手のひら側で、小指の延長線と手首の横皺が交差する部分
- 百会:頭頂部近くの中心に位置するへこみ
- 山根:左右の目頭の間
体をつねる
体をつねるのも、寝不足を解消する方法のひとつです。
人間は、痛みを感じると眠気が軽減される傾向にあります。これは脳が痛みを危険信号として受け取り、緊張状態に入るとされているためです。
つねると眠気覚ましに有効と言われている体の部位は、以下の通りです。
- 内腿
- 頬
- 手の甲
- 二の腕
- 足裏
- 耳
上記の部位は、皮膚が薄かったりツボが集まったりしているため、少しの刺激でも痛みを感じやすい傾向があります。
シャワーを浴びる
シャワーを浴びると、寝不足の症状が和らぐことがあるでしょう。
シャワーを浴びることは、交感神経を優位な状態に変化させ、活動のスイッチを入れる手段として有効と考えられています。さらに、水温を高めにすることで、体温や血圧が上昇しやすくなり、眠気が軽減される効果も期待できます。
冷たい水で体を冷やす
冷たい水で体を冷やすことは、寝不足の解消に役立つことが少なくありません。
人間は体温が下がると交感神経が優位になりやすく、身体が活動モードに切り替わる傾向にあります。身体が活動モードになると、血圧や心拍数が上昇して覚醒状態になり、眠気が軽減されやすいとされています。
太い血管が存在する首筋や手首、足首などを冷やすと効率的に体温を下げられるでしょう。また、冷却シートや冷却スプレーなどのアイテムを活用するのもひとつの手段です。
さらに、冷たい水で手を洗うことでも、身体を冷やす効果が期待できるでしょう。
体を動かす
寝不足を解消する方法のひとつとして、体を動かすことが挙げられます。
体を動かすことは、筋肉を刺激して交感神経を優位にするのに役立つでしょう。交感神経が優位になると、気分がリフレッシュされて眠気が緩和されると考えられています。
寝不足の解消に役立つ運動の例として、以下のようなものが挙げられます。
- 立ち上がって歩く
- 背伸びをする
- 手を開いたり閉じたりする
- 肩を回す
- 足首を回す
ストレッチをする
ストレッチは、眠気を覚まして寝不足を解消するのに役立つでしょう。身体を動かすことは、気分を切り替えて頭をすっきりさせるのに有効な手段と言われています。
ストレッチによって筋肉をほぐすことで、交感神経の働きが活発になることが多いです。そして、人間は、交感神経の働きが活発な状態では、眠気が軽減される傾向があります。
明るい方へ目を向ける
明るい方に目を向けると、眠気が覚めて寝不足が解消されることが多いです。人間は光を感じ取ると、眠気が発生しにくくなる傾向があります。
これは、眠気を感じる要因とされるメラトニンというホルモンが関係していると考えられているためです。暗い空間ではメラトニンの分泌が促進されやすい一方で、明るい空間ではその分泌が抑えられると言われています。
メンソールを首や鼻につける
メンソールを首や鼻につけるのも、寝不足の解消に有効な方法のひとつです。
メンソールを皮膚に塗ると、意識の覚醒が促されることがあります。これは、メンソールが肌に触れることで皮膚の冷たさを感じる神経が刺激され、ひんやりとした感覚を得やすいためです。
ガムをかむ
ガムをかむことで、寝不足を解消できる可能性があります。
ガムをかむ行為は、継続的に繰り返される顎の運動を伴うことが特徴です。この刺激によって、血流が促進されたり、脳の活動が高まったりすることで、眠気が軽減されると考えられています。
さらに、カフェインや糖分が含まれているガムなら、それらの成分が眠気を和らげるのに役立つ可能性があります。
寝不足にならないためにできる習慣
寝不足にならないためにできる主な習慣は、次の通りです。
- 朝食を食べる
- 毎朝決まった時間に起床する
- 運動を習慣化する
- ストレスを解消できることをする
- 就寝の数時間前までに夕食を食べる
- アルコールの摂取を控える
- 睡眠環境を整える
- 眠くなってから布団に入る
朝食を食べる
寝不足の予防に効果的な手段のひとつとして挙げられるのが、朝食を食べることです。
朝食をとると、各臓器や組織に備わっている末梢時計が調整され、体内時計が整いやすくなると言われています。これは、食事で炭水化物を摂取することで血糖値が上がり、インスリンというホルモンが分泌されるためと考えられています。
また、炭水化物とあわせて、たんぱく質も体内時計の調整に関与しているとされることが多いです。例えば、朝食では白米やトーストなどの炭水化物と、納豆や魚、肉といったたんぱく質を組み合わせて摂ることが推奨されることがあります。
毎朝決まった時間に起床する
毎朝決まった時間に起床することは、寝不足を予防する効果が期待できるでしょう。起床時間を一定にすることで、規則正しい睡眠サイクルが身につきやすくなります。
また、朝に起床して日光を浴びることができれば、体内時計のひとつである中枢時計のリズムが整いやすくなると言われています。
運動を習慣化する
寝不足を予防する方法のひとつとして挙げられるのが、運動を習慣化することです。運動によって体力を消費すると、心身が適度に疲れて休憩を欲するようになり、眠りに付きやすくなる場合が多いです。
さらに、運動すると活動と休息の切り替えがしやすくなったり、気持ちを落ち着かせやすくなったりする効果も期待できるでしょう。
ほかにも、自律神経の働きを整える作用や、幸せホルモンであるエンドルフィンの分泌によって気分が穏やかになる効果などがあるとされています。
これらの作用によって精神的なプレッシャーや不安感がやわらぐことで、眠りに入りやすくなると言われています。
しかし、就寝間近の時間帯に運動をすると、心身が活動モードになってしまい入眠が阻害される可能性が高いです。
運動は、午後から就寝の1~2時間前の時間帯に終わらせるようにすると、入眠への影響を抑えやすくなるとされています。
ストレスを解消できることをする
適度にストレスを解消すると、寝不足を予防できる可能性が高いと言われています。
ストレスを感じている状態だと、リラックスできずに眠ってしまい、睡眠の質が下がりがちです。
また、悩みごとについて考えすぎてしまい、スムーズに入眠できず寝不足になる可能性もあります。そのため、散歩や友人に悩みを話すなど、自身にとって行いやすい方法で、定期的にストレスを解消していくと良いでしょう。
就寝の数時間前までに夕食を食べる
就寝の数時間前までに夕食を済ませることは、寝不足を予防する有効な手段と言えるでしょう。食事をした場合、食べ物を消化するために数時間は消化器系の内臓が働き続けるとされています。
消化器系の内臓が活動した状態では、身体が活動モードになりやすく、スムーズな入眠が難しくなりがちです。そのため、就寝する約3時間前には夕食を済ませておくことが望ましいと考えられています。
アルコールの摂取を控える
寝不足を予防するのに有効な手段のひとつが、アルコールの摂取を控えることです。
アルコールの摂取は、さまざまな要因で睡眠の質が下がりやすく、寝不足の原因になると言われています。
例えば、アルコールの分解後に発生する「アセトアルデヒド」による影響で、睡眠中に目が覚めやすくなり、長時間の睡眠が妨げられやすくなります。
睡眠環境を整える
睡眠環境を整えることは、寝不足を解消するのに有効だと考えられています。
自分に合わない睡眠環境では、睡眠の質が下がったり、入眠が難しくなったりすることがあります。必要な分の睡眠が取れないと、身体の疲れが残ってしまうことが多く、日中に眠気を感じがちです。
なお、睡眠環境を整える際のポイントとして、以下のような内容が挙げられます。
- 自分の身体に合った寝具を使う
- 室温や湿度を適切な状態に保つ
- 寝室で騒音が聞こえないようにする
- 寝室を暗い状態に保つ
眠くなってから布団に入る
寝不足にならないためにできる習慣として、眠くなってから布団に入ることも効果的と言えるでしょう。
寝不足の状態になると、早く眠ろうと意識しすぎて、かえって焦りが生じやすくなります。しかし、焦ると交感神経が活発になってしまい、心身が活動モードに移行して余計に眠れなくなる可能性が高いです。
例えば、就寝の時間に眠気が来ない場合にも焦らずに、ゆっくりと呼吸に意識を向けたり、軽いストレッチをしたりして、心を静めると良いでしょう。
寝不足に関連するよくある質問
寝不足にならないためにどれくらいの睡眠時間が必要ですか?
成人であれば、寝不足を回避するのに必要な睡眠時間は7時間前後とされています。
厚生労働省の調査では、睡眠時間が7時間前後の人が、各種精神病や生活習慣病の罹患率が最も低いとされています。
しかし、必要な睡眠時間は個人の体質や年齢などによっても左右されるという考え方も一般的です。そのため、日中に眠気が発生しない程度の睡眠時間であれば、問題ないとされることが多いです。
寝不足になっている時の体のサインはありますか?
寝不足の状態では、さまざまな症状が体に現れると言われています。
寝不足になると、ストレスが増加したり、自律神経のバランスが崩れたりして、体にさまざまな悪影響が出がちです。
寝不足の代表的な症状は、以下の通りです。
- ストレスを感じやすくなる
- 体の疲れがとれにくくなる
- 集中力や判断力が低下する
- めまいや頭痛を起こしやすくなる
- 病気になりやすくなる
寝不足は何日で解消しますか?
寝不足だった期間に応じて、解消するまでにかかる日数も増える傾向にあります。
例えば、1日1時間睡眠が不足していた場合、寝不足を解消するのに4〜9日かかる場合が多いです。なお、寝不足の状態によっては、3〜4週間かかる場合もあるとされています。
睡眠負債とはどのようなものですか?
睡眠負債とは睡眠不足が常態化してしまい、心と身体に負担がかかっている状態のことを指す場合が多いです。
睡眠の時間や質が不足している状態が続くと、睡眠不足が借金のように積み重なってしまうと言われています。
例えば、8時間の睡眠が望ましいとされる人が、6時間の睡眠しかとれなかった場合、1日で2時間分の睡眠負債が発生すると考えられています。
【監修者プロフィール】

江東こころのクリニック院長
谷本 幸多朗医師
九州大学医学部卒業後、帯広第一病院にて救急医療や外科及び内科の研修を経験する。
2013年より久喜すずのき病院にて精神科急性期医療を後期研修し精神保健指定医となる。
2018年より江東区にて一般メンタルクリニックに加えて認知症デイケアを併設した物忘れ外来も行う精神科クリニックである江東こころのクリニックを開業し、現在に至る。
▼主な経験
・精神保健指定医の経験あり
・製薬会社主催の各講演会や地域の医療職対象の勉強会において講演や座長の経験多数あり