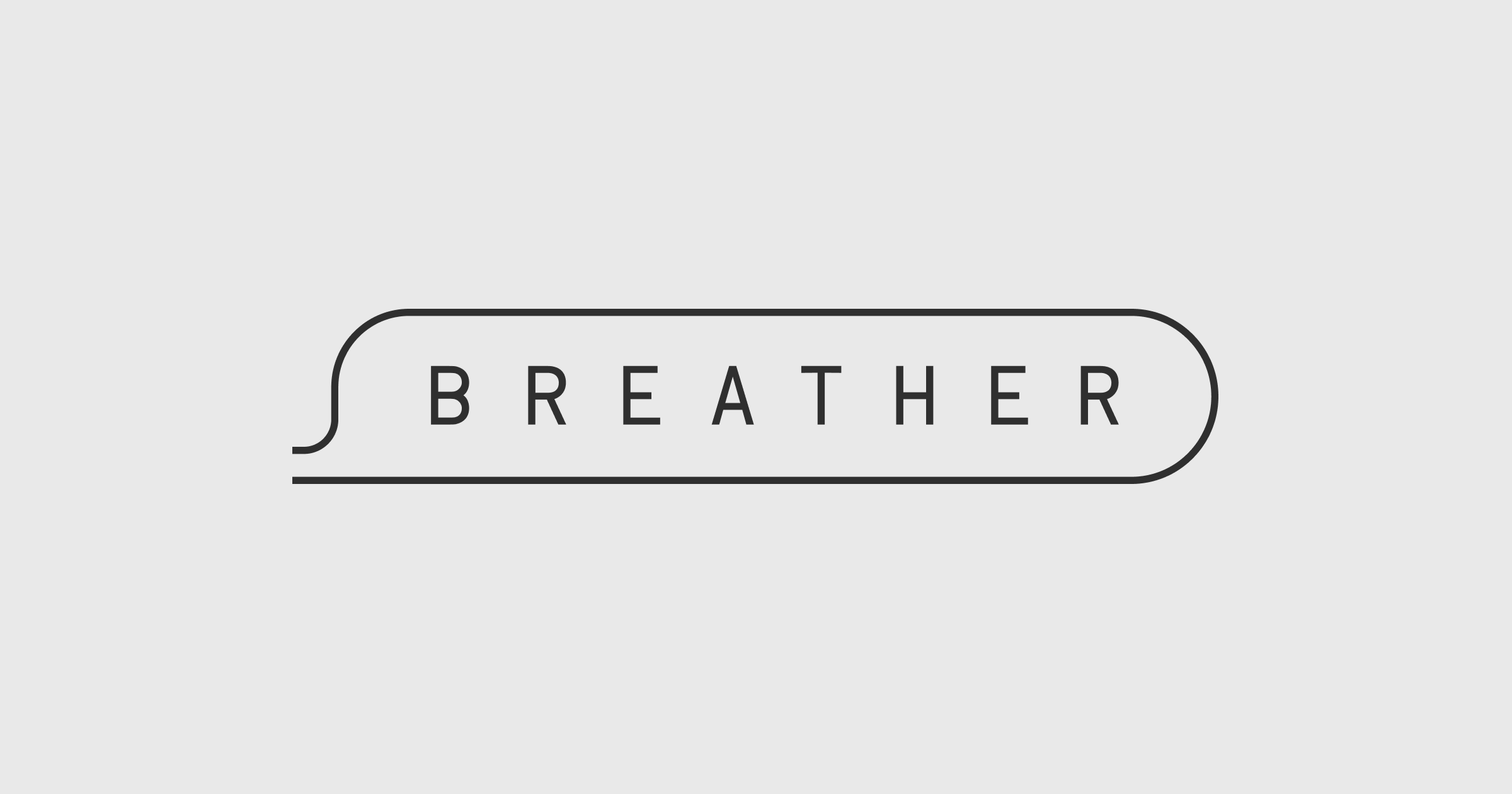目次
眠りが浅い原因・理由
眠りが浅い原因には、主に以下の6つがあるとされています。
- ストレスの蓄積
- 就寝環境の乱れ
- 就寝・起床時間の乱れ
- 過度な飲酒
- 頻尿
- 更年期
ストレスの蓄積
ストレスが蓄積すると、眠りが浅くなることがあります。
ストレスによって交感神経の働きが強くなると、夜になってもリラックスできず、副交感神経への切り替えがうまくいかなくなる場合があります。そのため、ストレスを抱える状態が続くと、たとえ入眠できたとしても眠りが浅くなる可能性が高いと言えます。
例えば、翌日のプレゼンテーションが不安で、眠ったものの浅い眠りが続き、夜中に何度か目が覚めてしまうことがあります。
さらに、ストレスの蓄積は、眠りを浅くするのみでなく、眠気自体を生じにくくさせると考えられています。
就寝環境の乱れ
就寝環境が整っていないと、眠りが浅くなることがあります。
ここで言う就寝環境とは、一般的に寝室の光量、温度、湿度、音、寝具の質などを含む総合的な睡眠条件のことを指します。
人間の脳は、周囲の環境からの刺激に敏感に反応すると言われています。そのため、就寝環境が悪いと脳が覚醒状態になりやすくなり、深い睡眠に移行しにくくなる可能性があります。
例えば、電気が明るすぎる部屋では眠りが浅くなり、少しの刺激で目が覚めてしまうケースも多いです。また、自分の体型や寝姿勢に合わない枕やマットレスを使用すると、眠りが浅くなる可能性があります。
さらに、引っ越しなどにより普段の生活環境が変わる際にも就寝環境が乱れがちになると言えます。そのような場合には、新しい環境に慣れるまでに時間がかかることを理解した上で、焦らずに対応することが大切です。
就寝・起床時間の乱れ
不規則な睡眠スケジュールは、体内時計を乱し、深い睡眠に入りにくくするとされています。
体内時計とは、「サーカディアンリズム」とも呼ばれる約24時間周期のリズムで、私たちの体のさまざまな生理機能を調整しているシステムです。
睡眠時間が日によってバラバラになることによって、メラトニンなどの睡眠ホルモンの分泌リズムが狂い、脳が睡眠と覚醒をうまく切り替えられなくなる可能性があります。その結果、体内時計のズレが生じることがあります。
例えば、平日の睡眠不足を休日に補う場合は要注意です。平日は短時間の睡眠で過ごし、休日に朝遅くまで寝る生活を続けると、睡眠のリズムが大きく乱れ、慢性的な睡眠不足につながる恐れがあります。
なお、平日と休日で2時間以上の睡眠スケジュールのズレがある場合は、体内時計が混乱し、質の高い睡眠をとることが難しくなると考えられています。
過度な飲酒
過度な飲酒は、眠りを浅くする原因になることがあります。
アルコールの過度な摂取は、睡眠中の脳の活動リズムを乱し、深い睡眠(ノンレム睡眠)と浅い睡眠(レム睡眠)のバランスを崩してしまい、質の高い睡眠が得られなくなる可能性が高くなると言えます。
例えば、寝つきをよくする目的で、就寝前にお酒を飲む「寝酒」の習慣は、確かに入眠を早める場合があります。しかし、深夜に眠りが浅くなり、目が覚めやすくなってしまうと言うデメリットがあります。
頻尿
夜間に何度もトイレに行く頻尿は、睡眠を分断し、眠りを浅くする原因の一つと言えます。
頻尿は、睡眠の連続性を妨げることで深い睡眠段階に移行させにくくし、睡眠の質全体を低下させる可能性があります。
例えば、夜間に2〜3回トイレに行くために起きるようになると、朝起きても体が重く、熟眠感が得られないことがあるでしょう。
このように頻尿が睡眠に大きな影響を与えている場合は、泌尿器科を受診して相談するようにすると良いでしょう。
更年期
更年期は、女性ホルモンの急激な変化の影響で、眠りが浅くなりやすい時期とされています。
一般的に更年期とは、閉経の前後約5年間の時期を指し、女性の身体に様々な変化が現れる期間です。多くの場合は、40代後半から50代に経験するとされています。
女性ホルモンの急激な変化は、自律神経のバランスを崩し、睡眠のコントロールに影響を与えてしまうと考えられています。
例えば、寝つきの悪さ、夜中のほてりや発汗、浅い眠りなどが更年期の症状で見られるケースが多いです。これらの症状は、日中のイライラや倦怠感にもつながる可能性が高いと言えます。
このように、症状が強く日常生活に支障をきたす場合は、婦人科で相談されることをおすすめします。
眠りが浅い時の改善・対策法
眠りが浅い時の改善方法として、主に以下の9つの方法が挙げられます。
- 深呼吸をする
- 就寝前の電子機器の使用を避ける
- 睡眠環境を整える
- 就寝前に入浴をする
- 運動を習慣化する
- 栄養バランスを意識した食事をする
- 生活習慣を整える
- 過度な飲酒を控える
- 専門家に相談する
深呼吸をする
就寝前の深呼吸は、睡眠の質を向上させる効果が期待できるでしょう。
ここで言う深呼吸とは、腹式呼吸を意識してゆっくりと息を吸い込み、ゆっくりと吐き出す呼吸法のことを指します。この深呼吸によって、副交感神経が優位になり、リラックス状態に導かれ、眠りが浅い状況を改善できると考えられています。
具体的な深呼吸の方法として、まず口から息を吐ききり、次に鼻から4~5秒かけてゆっくり息を吸い込みながらお腹を膨らませてみましょう。そして、口をすぼめて8〜10秒かけて息をゆっくり吐き出し、お腹をへこませます。この時、肩や胸ではなくお腹の動きを意識することが大切です。
就寝前の深呼吸に是非試してみると良いでしょう。
深呼吸習慣化デバイス「ston s」

- 「ston s」は、エナジードリンクでも、電子タバコでもない深呼吸を習慣化することを目的としたデバイス
- 罪悪感0で瞬間リフレッシュが可能
- 充電の必要がなく、どこでも持ち運びできる
就寝前の電子機器の使用を避ける
就寝前の電子機器の使用を避けることで、眠りが浅い状況を改善できる場合があります。
夜間にブルーライトを浴びると、体内時計が昼間と勘違いし、眠るための体の準備が妨げられる可能性があります。
例えば、眠れないからとSNSやニュースを見ると、コンテンツの刺激による精神的な興奮とブルーライトの影響で、眠りが浅くなる可能性が高いです。そのため、就寝の1〜2時間前からは電子機器の使用を控え、代わりに読書やストレッチなどのリラックスできる活動を取り入れると良いでしょう。
睡眠環境を整える
快適な睡眠環境に整えることで、眠りの質を高め、浅い眠りを改善できる可能性があります。
適切な睡眠環境は、身体的かつ精神的なリラックス状態を作り出すことで、深い眠りをサポートすると考えられています。
例えば、室温を夏は26℃前後、冬は20℃前後に設定し、湿度も40〜60%程度にしておくと理想的な寝室環境になると言われています。また、自分の体型に合った枕やマットレスを選び、締め付けのない綿素材のパジャマなど、リラックスできる服装で眠ることも大切です。
なお、睡眠中の騒音も良質な睡眠を妨げる要因となり得るため、音が気になる方は耳栓などの防音グッズを利用することも1つの方法です。
一方、静かすぎて眠れない方の場合は、自然系のBGMやホワイトノイズを活用してみると良いでしょう。
就寝前に入浴をする
就寝前の入浴は、眠りの質を向上させる効果が期待できます。
入浴する際は、睡眠に効果的な38〜40℃程度のぬるめのお湯に浸かることをおすすめします。この温度帯での入浴を行うことで、体の深部体温(内部の温度)を適切に調整し、睡眠への準備が促される可能性が高いです。
ただし、熱すぎるお湯は脳を興奮させてしまう恐れがあるため、注意が必要です。
なお、入浴は就寝の約2時間前までに済ませておくようにすると良いでしょう。
運動を習慣化する
適度な運動を日常的に行うことで、深い眠りを得やすくなる可能性が高いです。
定期的な運動は、ストレスホルモンの減少や睡眠に関わる脳内物質の分泌促進、体温調節機能の向上など、複数の経路で睡眠の質を高めることができると考えられています。
例えば、ウォーキングのような有酸素運動を日中に行うことで、夜間の睡眠が深くなる場合が多いです。また、ストレッチやヨガなどのリラックス効果の高い運動も質の高い睡眠を取りやすくなると言えます。
栄養バランスを意識した食事をする
栄養バランスの良い食事を心がけることで、眠りの質を向上できる可能性があります。
食事は体内で生成されるホルモンや神経伝達物質に影響を与えるため、睡眠の質に深く関わっていると考えられています。
例えば、以下の栄養素を含む食事を取るように心掛けると良いでしょう。
- トリプトファン(例:肉、魚、卵、牛乳、大豆製品、バナナ)
- グリシン(例:エビ、落花生、ホタテ、鶏肉)
- ビタミンB6(例:鶏肉、緑黄色野菜、サツマイモ、カリフラワー、鮭やアジなどの魚)
- 葉酸(例:枝豆、納豆、いちご、マンゴー、小松菜やブロッコリーなどの緑黄色野菜)
- マグネシウム(例:大豆製品、魚介類、野菜、海藻、ごまやアーモンドなどの種実類)
- ヘム鉄(例:牛ヒレ肉や豚ヒレ肉などの赤身肉、カツオやマグロなどの赤身魚、あさりやしじみなどの貝類)
- 非ヘム鉄(例:卵、大豆製品、海藻、ほうれん草や小松菜などの青菜類)
ちなみに、ほうれん草や小松菜などの非ヘム鉄の栄養素は、ビタミンCと一緒に摂ることによって吸収率を上げられる可能性が高いと言えます。
また、朝に食事を取ることによって、体内時計が調節されると考えられているため、無理のない範囲で朝食をとる習慣を作ると良いでしょう。
生活習慣を整える
生活習慣を整えることも、浅い眠りを改善する方法の一つと言えます。
生活習慣が整うことで体内時計が正常に働き、夜になると睡眠ホルモン(メラトニン)が適切に分泌され、自然と深い眠りにつきやすくなると考えられています。
生活リズムを整えるポイントは、以下の通りです。
- 毎日同じ時間に起きる
- 朝起きたらすぐに太陽の光を浴びる
- 毎日決まった時間に食事をとる
- 日中に30分程度の運動をする
- 夜21時以降はゆっくりと入浴などでリラックスする
- 就寝1時間前からはスマホやテレビを見ない
また、起きる時間を一定にするためにも、休日も平日と同じ時間にアラームをセットすると良いでしょう。
生活リズムをすぐに変えることは難しいため、無理のない範囲で、少しずつ良い習慣に近づけていくことが大切です。
過度な飲酒を控える
過度な飲酒を控えることで、眠りが浅くなる状況を改善できる可能性があります。
お酒を飲んだ直後は、神経活動を抑制してリラックス効果をもたらすことが多いです。しかし、時間の経過とともにアルコールの分解が進むと、逆に脳が刺激され、睡眠が浅くなりやすくなると言われています。
具体的には、量を日本酒なら1合程度に抑え、就寝の約3時間前までに済ませると良いでしょう。
また、毎日お酒を飲む習慣がある場合は、最初は週に2〜3日は休肝日を作り、徐々に回数を増やしていくというステップを踏むと良いでしょう。こうした工夫によって、アルコールに頼らず自然な眠りのリズムを整えられる可能性が高まります。
専門家に相談する
眠りが浅い状態が続く場合は、専門家に相談することで改善できる可能性があります。
眠りが浅さについて専門家に相談したい場合は、心療内科や精神科、内科の医師、睡眠外来の専門医などに相談すると良いでしょう。
また、眠りが浅い状態が続く背景には、ストレスや生活習慣の乱れ以外にも、うつ病などの精神疾患や睡眠時無呼吸症候群などの病気が隠れている可能性が高いです。そのため、睡眠の悩みに精通した医師に診てもらうことによって、適切な治療法を提案してもらえるケースも多いと言えます。
質の良い睡眠にするための対策を行っても、眠りが浅い状態が続く場合は専門家に相談すると良いでしょう。
眠りが浅いことによる影響
眠りが浅いことによる影響として、以下のようなものが考えられます。
- ストレスを感じやすくなる
- 記憶力が低下する
- 集中力や判断力が低下する
- 太りやすくなる
- 夢を見ることが増える
ストレスを感じやすくなる
眠りが浅い状態が続くと、ストレスを感じやすくなると言われています。
一般的に睡眠には肉体的な疲労の回復のみならず、ストレスの回復にも効果があると考えられています。しかし、眠りが浅く満足に睡眠がとれていない場合には、ストレス耐性が低下し、通常よりもイライラを感じることが多くなる可能性が高いです。
例えば、眠りが浅い状態が1週間続いた人は、通常であれば冷静に対応できる職場での小さなトラブルにも過剰に反応してしまうことがあるでしょう。
このように、浅い眠りが続く状態は、些細なことでイライラしたり、怒りっぽくなったりする原因となり得ます。
記憶力が低下する
眠りが浅い状態や睡眠時間の不足が続くと、記憶力が低下する可能性があるでしょう。
睡眠は記憶の定着や強化に重要な役割を果たしているため、睡眠の質が低下すると、新しい情報の記憶や学習効率に悪影響が出るとされています。
例えば、テスト前にしっかりと睡眠をとりつつ勉強した時は高得点を取れたのに、徹夜で勉強した時は同じ学習時間でも思うような結果が出なかった、というケースがあります。
これは睡眠中に学んだ内容が整理され、記憶として定着する働きがうまく機能しなかったことが影響していると言えます。
このような記憶力の低下を防ぐためには、睡眠時間を削らずに、寝る前の短時間でも集中して学習し、その後に良質な睡眠を取ることが効果的と言われています。
集中力や判断力が低下する
眠りが浅いと、集中力や判断力が低下することがあります。
眠りが浅く満足に睡眠が取れていない場合は、脳が完全に休まらず、日中の仕事や学業にも支障をきたすケースも多いです。
例えば、前日の睡眠が浅かった日は、仕事中にケアレスミスが増えたり、人の話を聞いても内容が頭に入ってこなかったりすることがあります。
また、集中力や判断力の低下は一時的なものにとどまらず、重大なミスや事故につながる恐れもあるため、日々の睡眠を見直すことが大切です。
太りやすくなる
眠りが浅い状態が続くと、食欲が増進し太りやすくなることがあります。
睡眠不足によって食欲を調節するホルモンの働きを乱し、満腹感を得られにくくなる可能性が高いです。その影響で、食べ過ぎを招きやすくなると言われています。
例えば、睡眠が浅く短時間しか眠れない生活を続けている人が、食事で多く食べすぎてしまい、体重が増えてしまったというケースは珍しくありません。
また、食べ過ぎによる肥満は、糖尿病や高血圧、心疾患などの複数の病気を招くリスクもあるとされているため、普段から規則正しい生活を意識しておくと良いでしょう。
夢を見ることが増える
眠りが浅いと、夢を見ることが増える場合があります。
一般的に睡眠には脳が活発に活動するレム睡眠と、脳が休息するノンレム睡眠があります。眠りが浅いとレム睡眠の時間が、相対的に長くなるため、夢を見る機会が増えると考えられています。
例えば、眠りが浅くなっている時には、夢の内容をはっきり覚えていたり、夜中に何度も夢を見て目が覚めてしまったりすることが多いです。
いつも夢を見ていたり、疲れが取れないと感じる場合は、睡眠のバランスが崩れている可能性が高いと言えます。
眠りが浅い人の特徴
眠りが浅い人の特徴には、主に以下の3つがあります。
- 疲れがとりにくい
- 感情の起伏が激しい
- 頭の回転が鈍くなる
疲れがとりにくい
眠りが浅い状態が続くと、睡眠による疲労回復がうまく進まず、疲れがとれにくくなることがあります。
睡眠中、体内では細胞や筋肉、臓器が休息と修復のプロセスを行っていると考えられています。眠りが浅くなることで、この働きがうまく機能しないと、疲労が回復しきらないまま日中を迎える可能性が高いです。
例えば、しっかり眠ったつもりでも朝から体が重く感じたり、週末に長く寝ても疲労感が抜けないといった状態が続く場合は、睡眠の質が影響している可能性があります。
疲労感が慢性化している時は、睡眠のみでなく日々の生活習慣やストレスとの関係も含めて、原因を見直すことが重要です。
感情の起伏が激しい
眠りが浅いと、些細なことで気分が変わりやすくなることが多くなりがちになると言えます。
眠りが浅い状態が続くと、脳の感情を落ち着かせる機能が発揮されにくくなると考えられています。その結果、イライラや不安を感じやすくなる可能性が高いです。
例えば、普段なら気にならないような一言に過剰に反応してしまったり、理由もなく気分が落ち込むことが増えた場合は、睡眠の質が影響している可能性があります。
なお、気分の波が大きい状態が続くと、人間関係や仕事のパフォーマンスにも影響しやすくなるため、早めに生活リズムや睡眠習慣を見直すことが大切です。
頭の回転が鈍くなる
頭の回転が鈍くなることも、睡眠が浅い人の特徴の一つと言えます。
睡眠が浅いと脳の休息が不足し、記憶の整理や情報処理の効率が下がるため、思考力や判断力に悪影響が出やすくなる可能性が高いです。
例えば、普段であれば急なトラブルや問題にも優先度を付け、柔軟かつ的確に処理できる人でも、睡眠不足により仕事の融通が利かず、意思決定のスピートが遅くなってしまうケースが見受けられます。
このような頭の回転が鈍く感じられる状態が長く続く場合は、睡眠の質以外に体調やストレスの影響も考慮した上で、必要に応じて医療機関に相談するのも一つの方法です。
眠りの浅さのセルフチェック方法
眠りの浅さをチェックする方法として、以下のような項目に当てはまることが多い場合は、睡眠の質が低下している可能性があると言えます。
以下の項目を参考に、日々の睡眠状態を振り返りながら是非チェックしてみてください。
- 朝起きた時に、ぐっすり眠った感じがしない
- 夜中に何度も目が覚める
- 夜中に目が覚めた後、なかなか寝つけない
- 夢を見る頻度が高く、眠った気がしない
- 日中に強い眠気や集中力の低下を感じる
- 睡眠時間は足りているのに、疲れが残っている
- 寝る直前までスマホやパソコンを見ている
- カフェインやアルコールを夕方以降も摂取している
なお、眠りの浅さの原因には、ストレスや生活習慣以外にも、うつ病や周期性四肢運動障害などの病気が原因となっている場合もあります。
浅い眠りに悩まれる方は、無理をせずに一度医療機関を受診してみることをおすすめします。
浅い眠りに関連するよくある質問
眠れない時の対処法は?
眠れない時には、以下の対処法を試してみると良いでしょう。
- 軽いストレッチで筋肉のコリをほぐす
- 38〜40℃のぬるめのお湯に、10〜15分ほど浸かる
- 好きな香りのアロマを焚く
- ヒーリング音楽や環境音(波の音、雨音など)を流す
- 照明を落として、間接照明などのやわらかい光に切り替える
睡眠にはどのような役割がありますか?
睡眠には、主に以下のような役割があるとされています。
- 体の疲れを取る
- 脳の働きを整える
- 成長ホルモンの分泌を促す
- 免疫力を高める
不眠症の種類にはどのようなものがありますか?
不眠症の種類として、以下のものが挙げられます。
- 入眠障害:寝つきに時間がかかる
- 中途覚醒:夜中に目が覚めてしまい、再び眠るのが難しくなる
- 早朝覚醒:朝の予定より早く目が覚めてしまい、そのまま眠れなくなる
- 熟眠障害:睡眠時間は足りていても眠った感じがせず、疲れが残る
それぞれのタイプによって対処法が異なるため、自分の状態を把握して対応することが大切と言えます。
また、上記のようなタイプの症状が同時に2つ以上みられるケースもあるため、注意が必要です。
【監修者プロフィール】

江東こころのクリニック院長
谷本 幸多朗医師
九州大学医学部卒業後、帯広第一病院にて救急医療や外科及び内科の研修を経験する。
2013年より久喜すずのき病院にて精神科急性期医療を後期研修し精神保健指定医となる。
2018年より江東区にて一般メンタルクリニックに加えて認知症デイケアを併設した物忘れ外来も行う精神科クリニックである江東こころのクリニックを開業し、現在に至る。
▼主な経験
・精神保健指定医の経験あり
・製薬会社主催の各講演会や地域の医療職対象の勉強会において講演や座長の経験多数あり