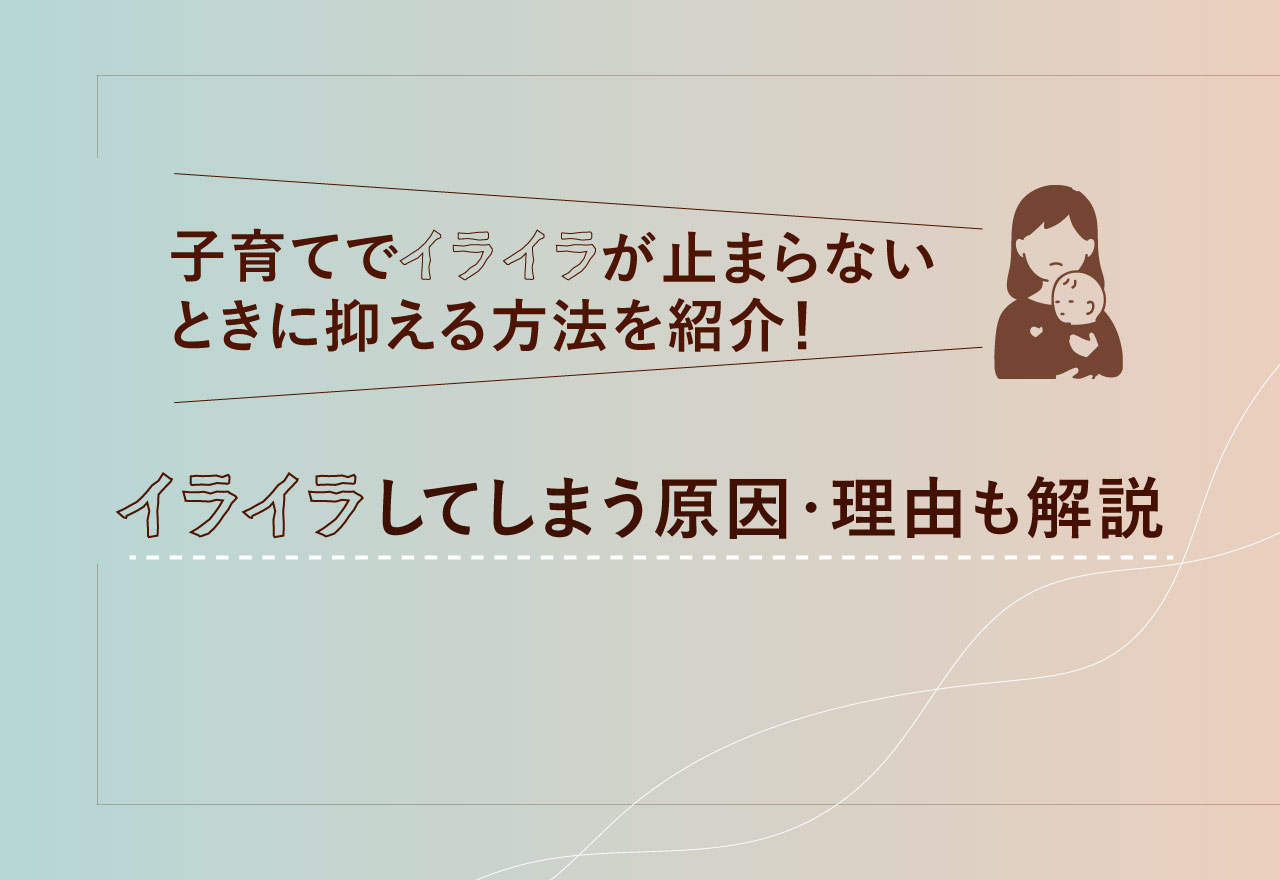目次
子育てでイライラする理由・原因
子育てでイライラする理由や原因について、主に以下の3つが考えられます。
- 子どもに関するイライラの場合
- 自分に関するイライラの場合
- パートナーに関するイライラの場合
子どもに関するイライラの場合
子どもが親の思い通りに行動してくれないことが原因で、イライラしてしまう場合があります。
多くの子どもは、大人の指示や想定通りに動くとは限らないものです。子どもの感情や気分によって、行動が左右されるため、親が計画していた通りに物事が進まないことが多いでしょう。
例えば、朝の忙しい時間に限って着替えを嫌がったり、ご飯を食べるのを拒否したりする場面が挙げられます。また、子どものために用意した食事や外出の予定を嫌がられたり、突然機嫌を損ねて泣き出されたりすると、無力感やイライラを感じることもあります。
そこで、あらかじめ子どもは思い通りにならない存在と理解しておくことで、イライラを感じたとき、気持ちに余裕を持てる可能性があります。
子どもが親の思い通りに行動しないことは、特別なことではなく自然な成長過程の一部だと言われています。そのため、完璧を求めすぎず、思い通りにならないのが当たり前と受け止めることで、ストレスを軽減することができるでしょう。
自分に関するイライラの場合
自分自身の睡眠不足や疲労の蓄積が、子育て中のイライラの大きな原因となっていることがあります。
産後の生活は、赤ちゃんの夜泣きや授乳によって睡眠が短くなりやすく、必要な休息をとれない状態が続くことが多いです。
そのため、育児や家事をこなす中で、心身の疲労が蓄積していくと、ホルモンバランスが乱れ、感情の起伏が激しくなる可能性が高いです。そうした心身の負担が続くと、イライラを感じやすくなる要因となり得ます。
さらに、体調やメンタルの崩れに気づかずに放置すると、イライラを自分のせいだと感じて自己否定につながる可能性があります。そのため、まずは体を休めることで、感情を安定させることが大切だと考えられています。
休息をとれない状態では、普段なら気にならない子どもの言動にも過敏に反応してしまい、イライラが爆発してしまうことがあります。その結果、怒りを子どもにぶつけてしまい、自己嫌悪に陥るケースもあります。
そのため、子育て中にイライラを感じたときは、まずは自分自身の体調を見直すことが大切だと言えるでしょう。「最近よく怒ってしまう」「体がだるい」と感じたら、睡眠や食事、休息をしっかり取れているかを確認しましょう。
パートナーに関するイライラの場合
家事や育児の負担が一方に偏ることで、パートナーに対して強いイライラを感じることがあります。
子育て中は、家事や育児のタスクが多く、休む時間すら取れないこともあります。そのような中で、パートナーが協力的でなかったり、夫が家事や育児は妻の役目と考えていると、不満やストレスが蓄積しやすくなります。
自分が育児をしているのにも関わらずパートナーが自由に過ごしている様子を見ると、不満が募り、イライラにつながりやすいです。また、育児の負担を一人で抱え続けると、心身ともに疲弊し、家庭内の関係悪化にもつながる可能性があります。
早い段階で負担の偏りをパートナーへ伝えることが、イライラを軽減し、良好なパートナーシップを築くためにも大切でしょう。
感情的になる前に思いを冷静に共有することで、相手に状況を理解してもらいやすくなります。
子どもに関する子育てのイライラを抑える方法
子供に関する子育てのイライラを抑える方法として、主に以下の3つが挙げられます。
- アプローチを変える
- ポジティブに考える
- 子どもに気持ちを伝える
アプローチを変える
子どもへの伝え方を少し変えることで、イライラを軽くし、親子の関係がスムーズになる場合があります。
子どもが言うことを聞かない理由は反抗ではなく、伝えたいことが伝わっていなかったり、理解できていなかったりすることが多いです。そのため、伝え方を見直すことで、子育てのイライラ軽減につながる可能性があります。
例えば、短く具体的に前向きな言葉を使って伝えると、子どもは内容を理解しやすく、行動にもつながりやすくなるでしょう。
また、子どもは大人とは異なるペースで物事を理解すると考えられています。したがって、こちらが伝えたつもりでも、実際に伝わっていない可能性があることを前提に接することが大切です。
そのため、一貫性を持って丁寧に伝え続けることで、子どもは少しずつ理解を深め、次第に反応や行動に変化が見られるようになるでしょう。
ポジティブに考える
子どもの行動や失敗を前向きに受け止め、ポジティブな声かけを意識することで、気持ちが軽くなり、イライラを感じにくくなることがあります。
子育てでは、失敗や思い通りにいかないことが多いです。そのたびに子どもを叱ったり否定的な言葉を使っていると、親も疲れてしまいますが、視点を変えることで気持ちに余裕が生まれるでしょう。
例えば、子どもが牛乳をこぼしたときについイライラしてしまうことがあります。しかし、自分で注ごうとチャレンジしたんだと、ポジティブに捉えると、失敗も前向きな経験に変えることができるかもしれません。
無理に前向きになる必要はありませんが、できていることや努力に目を向けると気持ちが楽になるケースがあります。そのため、怒りそうなときこそ、この経験も成長の一歩と捉えるように意識すると良いでしょう。
子どもに気持ちを伝える
子どもとの関係を良好に保つためには、イライラをためこまず、自分の気持ちを素直に伝えることが大切だと考えられています。
子どもは親の表情や口調に敏感だと言われています。感情的に言葉をぶつけられると不安になったり、自己肯定感が下がったりすることもあります。そのため、親自身はなぜイライラしたのか、どうして欲しかったのかを冷静に伝える姿勢が大切だと言えます。
また、親が自分の気持ちを丁寧に伝える姿勢は、子どもにとって感情表現の手本になる場合もあるという見解が多いです。
例えば、家事と育児が重なって余裕がないとき、「ちょっと疲れてるから少し休ませてね」と伝えると、子どもは理解しようとする姿勢を見せてくれる場合があります。
そのため、子どもに伝えたいことがあるときは、一方的に伝えるのではなく、子どもと向き合って話すようにすると良いでしょう。また、伝えるときは、短く落ち着いて話すと、子どもも話を聞きやすくなる可能性が高いです。
自分に関する子育てのイライラを抑える方法
自分に関する子育てのイライラを抑える方法には、主に以下の5つが考えられます。
- 深呼吸する
- 休息する時間を作る
- 考え方を変える
- 美味しいものを食べる
- 人に相談する
深呼吸する
イライラしたときは、まず深呼吸で気持ちを整えることが大切と言われています。
イライラしたときには、呼吸が浅くなりがちであるため、深呼吸をしてしっかり酸素を取り込むことで、心と体の緊張がほぐれやすくなると考えられています。また、怒りのピークは6秒程度と言われており、その間に深呼吸することで、衝動的な言動を防げる可能性が高いです。
そのため、子どもが言うことを聞かずにイライラが募ったとき、以下のように腹式呼吸を試してみましょう。
- 鼻からゆっくり3秒かけて息を吸い、お腹をふくらませる
- 口から3秒かけて息を吐き、お腹をへこませる
ちなみに、深呼吸はすぐにできる簡単な方法ですが、継続し習慣にすることでより効果を感じやすくなると言われています。
また、イライラを感じたときは、立ち止まって深呼吸をすることで、冷静な対応につながりやすくなる可能性があります。
深呼吸習慣化デバイス「ston s」

- 「ston s」は、エナジードリンクでも、電子タバコでもない深呼吸を習慣化することを目的としたデバイス
- 罪悪感0で瞬間リフレッシュが可能
- 充電の必要がなく、どこでも持ち運びできる
休息する時間を作る
育児中でも、自分のための休息時間を意識的に確保することで、イライラの軽減につながる可能性があります。
子育ては24時間気が抜けない仕事ですが、親自身のケアも同じくらい大切だと言えます。親自身が、何もしない時間や好きなことに集中するような休息できる時間を持つことで、心のリセットがしやすくなります。
また、疲れやストレスがたまっていると、心の余裕がなくなり、ちょっとした出来事でも感情的になりやすくなります。例えば、子どもが昼寝している間に読書や音楽を楽しんだり、パートナーが子どもを見ている間に近所のカフェでひと息つくなど、短時間でも自分のための時間を持ちましょう。
もし、まとまった時間がとれなくても、1日5分好きな香りをかいだり、目を閉じて深呼吸するのみでも気持ちが軽くなる場合が多いです。
自分の時間を持つことに、罪悪感を抱く必要はないでしょう。親が自分を大切にする姿は、子どもにも自分を大事にすることの大切さを伝えるきっかけになり得ます。
考え方を変える
子育てのイライラを減らすためには、考え方を変えることも有効な手段であると考えられています。
親はこうすべき、といった理想や固定観念に縛られていると、現実とのギャップによりストレスを感じやすくなります。
完璧な親であろうとするよりも、できる範囲で頑張れば良いと自分に優しくすることが、気持ちを軽くする一歩でしょう。
また、全ての家庭や子どもには個性があり、一つの正解に当てはめることは難しいと言えます。そのため、思い込みを手放すことで、柔軟に対応できるようになり、イライラしてしまう頻度も減っていく可能性があります。
例えば、子どもは約束を守るべきと考えていると、何度も忘れる子どもに腹が立ちやすくなります。そこで、子どもには繰り返し学ぶ時間が必要であると考え直すと、穏やかに対応できる可能性があります。
美味しいものを食べる
好きなものを食べることで、気持ちがリセットされ、イライラの軽減につながる場合があります。
好きなものを食べることは、脳や心に直接働きかけるリフレッシュ法のひとつとされており、自分の好きなものを食べると、心にゆとりが生まれ、育児の合間にホッとできる瞬間を作ることができる場合があります。
例えば、子どものお昼寝中にコーヒーとスイーツで一息ついたり、夜に高級アイスをこっそり楽しむといった工夫で、自分自身を労わっている人も多いでしょう。
このように、好きなものを食べることを、育児中の楽しみの一つとして取り入れることが大切でしょう。
人に相談する
子育てでイライラしたときには、信頼できる相手に相談することが効果的と考えられています。
悩みを言葉にすることで、自分の気持ちを整理できるのみでなく、相手から適切な対策や視点を得られることがあります。また、相談相手に共感してもらえることで安心感が生まれ、イライラを落ち着かせることができる可能性があります。
例えば、子どもの寝つきが悪く悩んでいた親が、自治体の子育て支援センターで相談したところ、睡眠環境の整え方を教えてもらい、徐々に改善したというケースもあります。
このように、悩み事は一人で抱え込まず、早めに相談することが大切でしょう。また、話しやすい人が身近にいない場合は、自治体や支援センターなどの公的な窓口を利用する方法もあります。
パートナーに関する子育てのイライラを抑える方法
パートナーに関する子育てのイライラを抑える方法として、主に以下の3つが挙げられます。
- パートナーに気持ちを伝える
- 家事代行やベビーシッターを活用する
- スケジュールを確認し合う
パートナーに気持ちを伝える
パートナーへのイライラを抑えるには、パートナーに自分の気持ちを素直に伝えることが大切だと言われています。
どんなに身近なパートナーでも、言葉にしなければ気持ちは伝わらないものです。そこで、気持ちを共有することで、相手に協力してもらいやすくなり、子育ての負担感やストレスが軽減される可能性があります。
また、感謝やお願いを伝えることで、パートナーとの関係性も前向きに変わりやすくなるでしょう。
不満を伝えるときは、「〜してほしい」ではなく、「〜してくれると助かる」「〜してもらえると嬉しい」と柔らかい言い回しで伝えると聞き入れてもらいやすい場合があります。
なお、感情的になってしまう場合には、直接伝えずに、LINEやメモに気持ちを書き出してから伝えると、言いたいことが整理しやすくなります。
また、不満を伝えるときは、タイミングも大切だと言えます。パートナーの機嫌が良いときやリラックスしている場面を選びましょう。感情的にならず、まずは感謝を伝えたうえで冷静に話すことが、受け入れてもらいやすくするポイントだと考えられます。
家事代行やベビーシッターを活用する
パートナーに関する子育てのイライラを抑えるには、家事代行やベビーシッターなど外部の手を借りることもひとつの手段です。
毎日の家事や育児をすべて自分のみでこなそうとすると、負担が大きくなり、心の余裕がなくなりやすい傾向にあります。
そこで、家事代行やベビーシッターなど、第三者の力を借りることで、物理的な時間のみでなく、気持ちにもゆとりが生まれる可能性があると考えられています。また、心に余裕ができることで、パートナーに対する不満やイライラも和らぎやすくなる可能性が高いです。
例えば、週1回の掃除を家事代行に任せたり、数時間のみベビーシッターを利用して自分の時間を確保すると、リフレッシュにつながります。
もし、他人を家に入れるのに抵抗がある場合には、宅配型の家事支援サービスや、一時預かり保育などから試してみるのも良いでしょう。家族やパートナーと相談して、無理なく利用できる方法を見つけることが大切だと言えます。
スケジュールを確認し合う
子育て中のパートナーへのイライラを抑えるには、スケジュールを確認し合うことが大切でしょう。
予定を共有することで、「どちらが何を担当するか」「どこでサポートが必要か」を事前に見える化できる可能性があります。また、相手の予定を理解していれば、負担の偏りやすれ違いが減り、自然と協力しやすくなるケースが多いです。
例えば、保育園のお迎えを担当する日や行事の共有など、日々の中で発生する子どもにまつわる予定を共有できるでしょう。このようにお互いの負担が見えることで、家事や育児の分担もしやすくなる可能性があります。
ただし、スケジュールの共有のみでなく、お互いのスケジュールを把握した上で、偏りに気がついて声をかけ合うなどの行動も必要と言えるでしょう。
さらに、確認するタイミングなども決めておくと、習慣化しやすくなります。
イライラを子どもにぶつける影響
イライラを子どもにぶつける影響には、主に以下の3つがあると考えられています。
- 主体性が育ちにくくなる
- 自己肯定感が低くなりやすくなる
- 感情表現が苦手になりやすくなる
主体性が育ちにくくなる
親のイライラを子どもにぶつけるようなことが続くと、子どもの主体性が育ちにくくなる可能性があります。
主体性は、子どもの健やかな成長に欠かせない能力だと考えられています。
イライラをぶつけられ続けた子どもは、失敗や否定を恐れて、自分の意思で動くより「怒られないように」行動するようになる可能性が高いです。このように、主体性が育たないと、自己判断力や自立心が育ちにくくなり、将来の人間関係や自己実現に影響する場合があると言われています。
例えば、親が日常的にイライラして、怒鳴ってばかりいると、子どもは怒られることを避けるために行動を控えるようになりやすいです。
その結果、子どもは自分で考えて試す機会が減り、常に周囲の顔色をうかがって行動するクセがついてしまう傾向があります。
親がイライラしてしまうこと自体は誰にでもあり得ます。感情をぶつけるのではなく、一呼吸おいて伝えることを意識することが、子どもの主体性を守るために大切でしょう。
自己肯定感が低くなりやすくなる
親のイライラが日常的に子どもに向けられると、子どもの自己肯定感が下がりやすくなると考えられています。
自己肯定感とは、一般的に自分には価値があると信じる気持ちのことを指すと言われています。
親から否定的な言葉を繰り返し受けると、自分は認められていないと感じやすくなり、自信を持つことが難しくなる可能性があります。
その結果、意欲が低下したり、感情が不安定になったりする場合があります。家庭内で良い子を装っても、家庭外で反動が出てトラブルにつながるケースもあるでしょう。
さらに、子どもは親の感情表現を見て育つと言われています。親が自分の感情をコントロールする姿を見せることで、子どもも感情を整理しやすくなると考えられています。
日常の中で「うまくできたね」「頑張っていたね」と言葉をかけることでも、子どもの心には大きな自信が生まれることがあります。このような小さな積み重ねが、子どもの自己肯定感を支える土台になるでしょう。
感情表現が苦手になりやすくなる
親のイライラを日常的に受けて育つと、子どもは感情表現が苦手になると考えられています。
感情表現とは、一般的に自分の気持ちや欲求を言葉や態度で伝える力のことです。
これは、人との良好な関係づくりや自己理解に欠かせない能力だと言われています。この感情表現の力は、安心感がある環境の中でこそ育まれていくと考えられています。
しかし、子どもが感情を出すたびに否定されたり怒られたりすると、気持ちを伝えるのは悪いことだと学習してしまう場合があります。その結果、感情を押し殺す癖がつき、自分の気持ちを言えないまま成長してしまうこともあります。
例えば、子どもが物事をやりたくないと言ったときに、その感情を親が強く否定すると、次第に本音を口にできなくなる可能性があります。
子どもが気持ちを表現したときは、まず受け止める姿勢が大切だと言えます。
子どもにイライラをぶつけた時の対処法
子どもにイライラをぶつけた時の対処法として、主に以下の3つがあると言われています。
- 愛情が伝わるように接する
- 子どもとコミュニケーションをとる
- 誠実に謝る
愛情が伝わるように接する
子どもにイライラをぶつけてしまった時には、その後、愛情がしっかりと伝わるように接することが大切だと言われています。
親に怒られた時、子どもは嫌われたと感じ、不安になっている可能性が高いです。そのため、不安を取り払ってあげられるような関わり方が必要であると考えられています。
そこで、イライラをぶつけてしまった時は、その後にしっかりと子どもに愛情を伝えるようにしましょう。そうすることで、自分は大切な存在なんだと、子どもは実感できる場合が多いです。
これは親子の信頼関係を守るうえでも重要であると考えられています。言葉で気持ちを伝えたり、抱きしめたりすると、子どもの心はホッとするケースが多いです。
なお、感情的に怒ってしまった自分を責めすぎる必要はないでしょう。大切なのはその後のフォローだと言えます。
この時、物で機嫌を取るのではなく、言葉や触れ合いで愛されているという安心感を伝えることが子どもの心の安定につながると考えられています。
子どもとコミュニケーションをとる
イライラをぶつけた後は、子どもの話を丁寧に聞き、気持ちを言葉にする手助けをすることが大切です。
子どもはまだ自分の気持ちをうまく言語化できないことが多く、ふてくされたり怒ったりする形で表現してしまうことがあります。そのようなときこそ、話を聞きながら気持ちを引き出し、どう感じたかを一緒に整理してあげると、心の安定につながる可能性が高いです。
親の手助けによって気持ちを整理し、言葉にできるようになると、自分でも感情を理解しやすくなり、イライラや不満をおだやかに表現できるようになります。
また、親に自分の気持ちを分かってもらえたという安心感が、親子の信頼関係を強くしてくれると考えられています。
例えば、子どもがふてくされた様子を見せたときは、無理に話をさせようとせず、落ち着いたタイミングで優しく声をかけることが大切でしょう。さらに、嫌な気持ちになったのか、不安だったのかなど、子どもの気持ちを一緒に整理するように関わることで、感情を言葉で表す練習につながると考えられています。
また、子どもが話し出すまでに時間がかかることもありますが、急かしたり問い詰めたりするのは逆効果です。
大切なのは、子どもの気持ちを否定せずに受け止める姿勢でしょう。なお、言葉でうまく話せない子どもには、遊びや絵などを通じて気持ちを表現する方法も役立つ場合があります。
誠実に謝る
子どもにイライラをぶつけてしまったときは、自分の言動を認めて、誠実に謝ることが大切だと言えます。
謝るという行動は、自分の感情が行き過ぎたことを認め、相手の気持ちを大切にする姿勢でもあります。また、親が自分の非を認める姿は、子どもにとっても感情の扱い方を学ぶ大きな手本になるでしょう。
理由もわからず怒られた子どもは、不安や戸惑いを抱えたまま過ごす可能性があります。謝罪とフォローがあることで、安心感が生まれ、親子の信頼関係を守ることにつながると考えられています。
例えば、感情的になって怒ってしまった後は、ひと呼吸おいてから気持ちを落ち着け、怒りすぎたことを素直に伝えるようにしましょう。また、言葉のみでなく、抱きしめたり頭をなでたりするようなスキンシップを添えることで、子どもはより深く愛情を感じ取りやすいです。
大切なのは、自分の感情を見つめ直し、子どもの気持ちに寄り添うことだと言われています。普段から「ありがとう」や「ごめんね」が自然に行き交う関係性が、子どもにとって安心感がある環境となり得ます。
子育てでのイライラの具体例
子育てでイライラを感じる場面は、日常のあらゆるシーンに潜んでいます。
子育ては思い通りにいかないことの連続でしょう。子どもの言動や夫婦間の役割分担など、日々の小さな積み重ねが、知らず知らずのうちにストレスとなり、イライラにつながることがあります。
そこで、イライラを感じやすい場面を知っておくことで、自分の感情に気づき、対処の第一歩を踏み出しやすいと言えます。
子育てでイライラする場面には、以下のようなものが挙げられます。
- 素直に謝らない
- 外出先で騒ぎ出す
- 片づけをしない
- 時間ギリギリまで動かない
- 明らかなウソをついてごまかす
- パートナーが育児や家事に協力せず、負担を妻に任せきりにする
例えば、子どもが素直に謝らないときです。明らかに悪いことをしたのに、なぜ一言「ごめんなさい」が言えないのかと、つい感情的になってしまうことがあります。
また、外出先で騒ぎ出すと、周囲の目が気になって焦りやイライラが募ることがあります。この時、子どもに落ち着くように声をかけても、なかなか聞いてくれないと疲れてしまうでしょう。
毎日の生活の中では、片づけをしないことでイライラが積もることもあります。出しっぱなしのおもちゃを片付けるように何度も注意しても改善されないと、ついイライラしてしまうものです。
さらに、朝の準備を始めず、時間ギリギリまで動かないという行動も、忙しい平日の朝には大きなストレスになり得ます。声をかけても動かず、毎朝のように同じやり取りが続くと、疲れがたまりやすいです。
明らかなウソをついてごまかすことも、親としては気になるポイントでしょう。手洗いや宿題などについて確認したときに、実際には終わっていないにもかかわらず「やった」と答える場面があると、不信感や悲しさが入り混じったイライラにつながることがあります。
そして、忘れてはならないのがパートナーが育児や家事に協力せず、すべての負担を妻に任せてしまうケースです。自分が子どもの世話に追われている中で、何もせずに過ごすパートナーの姿を見ると、不公平感や孤独感から怒りや虚しさが募ることもあります。
イライラを感じること自体は、誰にでもある自然な反応です。大切なのは、「なぜイライラしたのか」「どの場面でそう感じたのか」に気づくことだと言えます。
その気づきが、感情を落ち着けたり、対処法を探したりする第一歩になる場合が多いです。
子育てでイライラが止まらない病気
子育てでイライラが止まらない場合、育児ノイローゼの可能性があります。
育児ノイローゼとは、育児によるストレスや疲れが心身に大きく影響し、気持ちが不安定になってしまう状態を指すと言われています。
なお、育児ノイローゼは病名ではありません。子育て中のイライラ、不安、孤独感、そして気力や興味の喪失など、さまざまな精神的症状があらわれる状態をまとめて「育児ノイローゼ」と呼ぶことが一般的です。
育児ノイローゼになると、以下のような症状が見られる場合があります。
- イライラの増加
- 気力や集中力の低下
- 興味・関心の喪失
- 悲観的な思考
- 不眠・過眠などの睡眠トラブル
- 食欲の変化(過食または拒食)
- 家族への攻撃的な言動
このように、イライラが止まらず、つらさを感じたときは、一人で抱え込まず、市区町村の子育て相談窓口などを頼ってみると良いでしょう。人に相談することで、心が少し軽くなることがあります。
子育てのイライラに関するよくある質問
子育てでしんどい時期はいつですか?
子育てでしんどい時期は、新生児から3歳頃までと言われています。
新生児期は、出産のダメージが残る中で、頻回授乳や寝不足が続き、初めての育児に不安を感じやすい時期です。
その後も、1〜2歳は自我が芽生え始め、2〜3歳ごろにはイヤイヤ期が始まるなど、成長とともにまた違った辛さを感じることが多いです。言葉が通じず、危ないことも分からない年齢の子どもを相手にするのは、体力的にも精神的にもきつくなることが多いでしょう。
子育てのイライラのピークはいつですか?
子育てのイライラをピークに感じるのは、生後9カ月〜1歳半頃の後追い時期だと言われています。
この時期の子どもは、トイレや洗濯、料理などで少しの間母親がそばを離れてしまって姿が見えないと、強い不安を感じ、大泣きして追いかけてくることがあります。
そのため、この時期の母親は、自分の時間も心の余裕も奪われてしまうことが多いでしょう。
子育てが楽になるのは何歳頃ですか?
子育てが楽になるのは、小学校入学前後の6歳頃だと言われています。
6歳頃は、トイレや食事、着替えなどの基本的な生活が一人でできるようになり、親の手伝いが必要となる場面が減る傾向にあります。
さらに、子どもが親の言うことを理解し、意思の疎通がスムーズになるため、精神的にも余裕が生まれる可能性があります。
ただし、送迎や見守りが必要な場面はまだ多く、完全に手が離れるわけではないため、注意が必要です。
【監修者プロフィール】

江東こころのクリニック院長
谷本 幸多朗医師
九州大学医学部卒業後、帯広第一病院にて救急医療や外科及び内科の研修を経験する。
2013年より久喜すずのき病院にて精神科急性期医療を後期研修し精神保健指定医となる。
2018年より江東区にて一般メンタルクリニックに加えて認知症デイケアを併設した物忘れ外来も行う精神科クリニックである江東こころのクリニックを開業し、現在に至る。
▼主な経験
・精神保健指定医の経験あり
・製薬会社主催の各講演会や地域の医療職対象の勉強会において講演や座長の経験多数あり